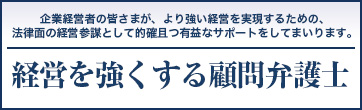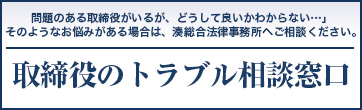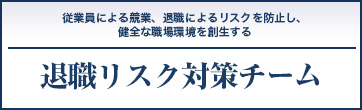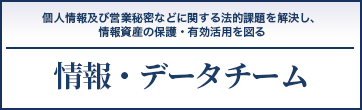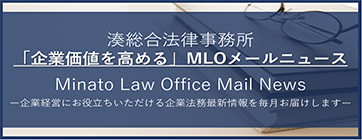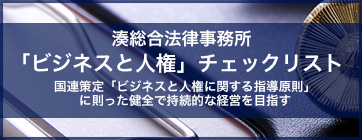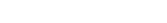特別受益・・・相続の現場で現実に起こっている熾烈な問題とは!(その2)
タイトル
| 父Aは、10年ほど前に、長男である私Bが家を継ぐということで、父Aが借地権を設定して、所有していた建物(当時借地権と合わせて7000万円相当)を贈与してくれました。家を継ぐ以上は、特別受益の持ち戻しは免除されておりました。
私には弟Cがおりますが、父Aは、弟Cは家を継ぐわけではないということで、何も贈与されませんでした。 父Aには愛人Dがいたことが発覚し、すでに母とは離婚しております。 父Aはその愛人Dに8年ほど前にマンション5000万円相当を贈与しています。父Aと愛人Dはその後も籍は入れておりません。 父Aは、3年ほど前から認知症の症状が進行し、私Bが父Aから贈与してもらった上記マンションで同居するようになりました。ところが、1年前に私Aが外出している間に、認知症の進行のために、火の不始末から建物を全焼させてしまいました。 父Aは、3ヶ月前に亡くなったのですが、亡くなった当時はすでに遺産らしいものはほとんどありませんでした。 にもかかわらず、私Bと愛人Dは、弟Cから、遺留分減殺請求を受けました。しかし、私Bは父Aから特別受益持ち戻し免除を受けていますし、すでにこの建物は父Aの火の不始末によりすでに焼失しています。もし父Aが焼失させなければ亡くなった当時の借地権付きの建物の時価は3000万円程度はあったと思います。このような状況でも、私は弟Cから遺留分減殺請求を受けることになるのでしょうか? また、父Aが亡くなった当時、愛人Dが贈与を受けたマンションの評価額は1600万円程度だったようですが、本件の場合、愛人Dも遺留分減殺請求を受けることになるのでしょうか? |
今回は、前回に続いて特別受益に関する熾烈な争い第二弾です!
今日は、弁護士も悩むようなかなり難しい話しをします。じっくりと読んでいただけたらと願っております。
(相続人と遺留分割合の確定)
まず、相続人と遺留分割合を確定させましょう。
父Aと妻はすでに離婚していますから、妻は相続人ではありません。
また愛人Dは入籍しませんでしたから相続人ではありません。
したがって、父Aの相続人はBと弟Cだけということになり、弟Cの遺留分割合は4分の1ということになります。
(弟Cは愛人Dに遺留分減殺請求することができるか)
まず、愛人Dは、父Aから8年前に5000万円相当のマンションの贈与を受けているのですが、弟Cからの遺留分減殺請求を受けることになるのでしょうか?
この点は、民法1030条の問題になります。同条によれば、贈与が被相続人が死亡する1年間以内であれば、当然に遺留分減殺請求の対象になるが、それ以前の贈与であれば、贈与当事者が、遺留分権利者の遺留分を侵害することになると認識していた場合に遺留分減殺請求の対象となるということになります。
本件は、8年前に贈与されていますから当然に遺留分減殺請求の対象とされるというのではなく、8年前に父Aと愛人Dの双方が、弟Cの遺留分を侵害することになると認識していた場合に、遺留分減殺の対象とできることになります。
したがって、弟Cがかかる事実を証明できた場合に、愛人Dに対して、5000万円÷4=1250万円の遺留分減殺請求をすることができることになります。
(弟CはBに遺留分減殺請求することができるか)
次に、Bに対して遺留分減殺請求できるかどうかは、さまざまな論点があり、すぐに結論を出すことはできません。
まず、Bは、父Aから借地権付き建物の贈与を受けているのですから、これは特別受益に該当します。これは問題ないでしょう。
問題は、Bが父Aから特別受益の持ち戻しの免除を受けているという点です。Bは、みなし相続財産を算定するときには、特別受益たる贈与価額は持ち戻さなくてもよいわけですが、そのことが遺留分額の算定にも影響して、遺留分額算定の基礎となる財産額に算入しなくても良いということになるのでしょうか。
この点については、特別受益があった場合には、その持ち戻し免除の意思表示があろうがなかろうが、必ず遺留分額算定の基礎財産額に算入しなければならないとされています。
なぜなら、そのように解しないと、遺言者が、生前に多額の贈与をしておいて持ち戻しの免除をすることによって、遺留分の基礎財産をいくらでも減らすことができることになってしまって不合理な結果となるからです。
では、次に、Bも愛人Dと同様に、民法1033条により、父Aの死亡時から1年内か否かで、受贈額が遺留分算定の基礎財産に組み入れられるかどうか扱いが変わるのでしょうか?
この点は、Bは相続人ですが、愛人Dは相続人ではないという点が分水嶺となります。つまり、民法1030条は相続人ではない者に適用される条文で、相続人には適用されないのです。
なぜ、そんな違いがでてくるのでしょうか?
その理由は、遺留分に関して規定されている民法1044条が、遺留分には、民法903条(期間制限を設けていない)を準用すると明記しているからです。
すなわち、民法903条は、遺産分割の際の相続取り分を決める際の基礎となる財産に、「相続人が」生前に特別受益を受けているときは、期限を設けることなくすべて参入すると規定しています。1044条は、このような903条を準用していることから、遺留分を計算する場合、「相続人」に対する生前贈与は、民法1030条にかかわらず、すべて計算の基礎にされると解されることになるのです。
したがって、Bは、弟Cから、遺留分減殺請求を受けることになります。
(建物が焼失していても遺留分減殺請求されるのか?)
もっとも、Bは、父Aから借地権付きの建物の贈与を受けているのですが、建物はすでに焼失してしまっています。建物が焼失してしまったので、借地権も同時に消滅してしまっています。
ですから、Bは、父Aが亡くなったときには、建物所有権も借地権も有していなかったわけです。
にも関わらず、Bが弟Cから遺留分減殺請求を受けるというのは酷なのではないでしょうか?
この点については、この借地権付き建物が、「Bの行為によって」滅失したときは、相続時に、当該建物が原状のままそのまま残っているものと評価され、遺留分減殺請求をされることになります。
その理由は、ここでも先ほど出てきた遺留分に関する民法1044条が、特別受益に関する904条を準用しており、「受贈者の行為によって」贈与の目的物が滅失した場合には、相続開始時に原状のまま存在したものとみなすとされているからです。
そうしますと、今回、この借地権建物を焼失させたのは、父Aであり、受贈者であるBではありません。ですから、原則として、「Bの行為によって滅失した」とはいえず、Bは責任を負わなくて良いことになります。
もっとも、当時、Bは、認知症の父Aと同居していたわけですから、父Aが火の不始末などを起こして、第三者に損害を被らせることのないようにすべき注意義務を負っていたと解する余地があります。
したがって、もし、このような注意義務を負っていたにもかかわらず、その義務を怠ったということでしたら、Bには過失が認められることになります。そうなりますと、借地権付き建物を焼失させたことが「Bの行為」と評価されることになります。この場合には、父Aが死亡したときの評価額2000万円÷4=500万円の遺留分減殺請求を受けることになってしまいます。
特別受益や、遺留分に関しては、相続紛争の中で特に熾烈を極めることがある分野です。今回ご紹介したテーマは少々難解だったかもしれませんが、雰囲気を体感していただけたらうれしく思います。
| 第903条第1項
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
第904条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
第1029条第1項 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
第1030条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
第1044条 (中略)903条並びに904条(特別受益者の相続分)・・・(中略)の規定は、遺留分について準用する。 |
事業承継の関連ページ
- 事業承継
- 認知症が招く法的トラブル その1
- 認知症が招く法的トラブル その2
- 認知症が招く法的トラブル その3
- 特別受益・・・相続の現場で現実に起こっている熾烈な問題とは!(その1)
- 特別受益・・・相続の現場で現実に起こっている熾烈な問題とは!(その2)
- 終末を考える際の対策
- 高齢化社会ニッポン。お嫁さんを守ることは大きな社会問題だ!
- 認知症患者が他人に損害を負わせたら、 家族はどんな責任を負うのか!?
- 遺産の預貯金は親の死亡後すぐに払い戻せるの?
- 遺留分対策ってどうやってやるの!?
- 会社に多額の連帯保証があって事業承継に二の足を踏んでしまうときは!?
- 思い込みは本当に危険! 悲惨な末期を辿ることになる!
- 子供への株式の譲渡
- 子供への土地の譲渡
- 遺言の作成
- 社長と認知症
取扱分野
- 顧問契約
- 契約書
- ESG・SDGs
-
労務問題
- 労務問題
- 湊総合法律事務所のIT業界労務特化コンサルティング
- 人事労務の解決事例
- 同一労働同一賃金の基礎知識とポイント
- 育児休業(育休)復帰後の職務変更・賃金減額について
- パタニティ・ハラスメント(パタハラ)対策
- 社員(従業員)を解雇するには?解雇できる条件について弁護士が解説
- 解雇紛争の予防と対処
- セクハラ被害を申告されたら
- 採用内定を取り消したいとき
- 試用期間中の社員に問題があるとき
- 本採用を拒否するには
- 従業員の犯罪行為(1):自宅待機命令・賃金支払義務
- 従業員の犯罪行為(2):起訴休職処分
- 労働条件の不利益変更
- 改正労働契約法第18条の解説
- 【退職方法に関するご相談】
- Q:従業員に会社を辞めてもらいたい場合、会社は、どのような対応を取るのが適切なのでしょうか。
- Q:会社が従業員を解雇しても、解雇の要件を満たさない場合には解雇が無効となると聞きました。解雇の要件とは具体的にどのようなものでしょうか?
- Q:本採用拒否や採用内定取消しは、どのような場合に有効、無効となるのでしょうか。 また「試用期間」や「採用内定」についても教えてください。
- Q:退職勧奨が違法となるのは、どのような場合でしょうか?
- Q:従業員に対して退職勧奨を行いたいのですが、前向きに自主退職を考えてもらうためどのように進めていくのが望ましいでしょうか?
- Q:退職勧奨の面談時において、会社が留意すべき点は何でしょうか?
- Q:退職にまつわるトラブルを防止するために、注意すべきポイントは何でしょうか?
- フリーランスにおける競業避止義務の状況~内閣府発表を受けて
- 退職後従業員の競業避止義務について弁護士が解説
- 不動産
-
取締役・取締役会
- 【解決事例】取締役に関する法律相談と当事務所の解決事例
- 【解決事例】退任取締役(少数株主)との紛争を裁判上の和解により解決した事例
- 【解決事例】取締役の違法行為差止仮処分を申し立て、同手続中で和解が成立した事例
- 【解決事例】退任取締役の未払役員報酬全額の支払いを認める判決を獲得した事例
- 【解決事例】子会社から対象会社の株式の譲渡を受け持株比率を変更することで取締役の退任を実現した事例
- 取締役に関する紛争(取締役間の紛争、会社と取締役との間の紛争、株主と取締役との間の紛争等)
- 取締役(役員)の解任を行う際の具体的な手続き・登記申請の方法について弁護士が解説
- 取締役が負う責任・賠償リスクの軽減方法とD&O保険の活用~会社法に詳しい弁護士が解説
- 取締役会に関する会社法上の規定について弁護士が基礎知識から解説
- 取締役会・株主総会の議事録とは?記載事項・リスクについて弁護士が解説
- 取締役会議事録記載事項について弁護士が解説
- このような決議事項に注意しよう(取締役会)
- 取締役会決議についての過去の不備をどうフォローするか
- 取締役会での決議案件
- 取締役会の決議方法
- 取締役会の招集
- 取締役会の招集手続
- 取締役会の招集通知
- 経営判断の原則が適用される場合とは?
- 取締役の経営上の判断によって会社に損害が生じた場合
- 取締役の報酬の減額
- 特別利害関係取締役とは
- 中小企業における株主総会・取締役会の実態と必要性について
- 定款に規定することにより安定した経営を行う方法
- 譲渡制限株式について譲渡承認請求を受けた。どう対応すればよいか?
- 取締役会対策に関する料金表
- 【取締役に関するご質問】
- Q 退任した取締役から退職金の支払いを請求された。どうすればよいか?
- Q 合わない(反対派)の取締役を辞めさせたい。
- Q 突然取締役を解任された。どう対応すればよいか?
- 【Q&A解説】会社に損害を与えた取締役の責任について損害賠償請求を提起が可能な場合とは?
-
産業廃棄物
- 廃棄物処理法にまつわる企業リスクについて
- 役所に提出する報告書に関する相談・解決事例~廃棄物処理法に詳しい弁護士が解説
- 廃棄物処理法違反の事実が判明した際の対応に関する相談・解決事例
- 廃棄物処理法に定める欠格要件該当によって許可が取り消されないようにするために
- 廃棄物処理法上の行政対応に関する法的サービスについて
- M&Aによる廃棄物処理業の事業承継
- 廃棄物処理に関する「よくあるご質問」
- 廃棄物処理業界における改善命令・措置命令・事業停止・許可取消
- 産業廃棄物処理法違反の事例と刑罰について
- 産廃・産業廃棄物に関する行政処分の種類と適用
- 産廃に関するコンプライアンス体制の樹立
- 廃棄物処理・運搬業の許可
- 委託業者が不法投棄した責任
- 廃棄物処理法の概要
- 廃棄物処理法の目的を理解する
- 廃棄物処理法に関する主な判例
- 産廃事業リスクに関する 意識の改革
- 平成22年度廃棄物処理法改正
- 平成29年度廃棄物処理法改正
- 産業廃棄物処理業の法律問題
- 改善命令・措置命令・事業停止・許可取消
- 産業廃棄物
- 消費者問題
-
株主総会
- 株主総会
- 取締役会・株主総会の議事録とは?記載事項・リスクについて弁護士が解説
- 株主総会の一般的な対策について~弁護士による同席・出席~
- 「来期の配当アップを約束して欲しい」と求められたら
- 株主一人で何問も質問しようとする場合の対処法
- 取締役の解任を求められた場合の対処法について弁護士が解説
- 総会屋対策
- 不祥事があった場合の対策
- 株主から質問状が送られてきた際の回答方法や対処法を弁護士が解説
- 譲渡制限株式について譲渡承認請求を受けた。どう対応すればよいか?
- 取締役会設置会社の株主総会の開催・運営をめぐるリスク
- 株主総会の決議事項について弁護士が解説
- 過去の不備をどうフォローするか
- 株主総会決議の瑕疵の例
- 株主総会決議の瑕疵に対する訴え
- 書面投票制度と電子投票制度
- 株主総会参考書類等の電子提供制度を導入したい
-
医療機関
- 医療機関
- コロナ禍の医療機関・病院における労務問題
- 医師から当直業務(宿直業務・日直業務)について残業代請求を受けた。 当直手当を支払っているが、別途残業代を支払う必要があるのか?
- 医師から残業代請求を受けた場合、 医療機関(病院、クリニック)としてどのように対応すべきか?
- 医療過誤の責任
- 医療紛争の流れ
- 医療事故の際の患者対応
- 医療事故の際の証拠保全
- 患者に対する説明義務
- 刑事手続きにおける取調べ
- 医療現場における法律知識
- 第1 医療事故に関する法律知識の基礎
- 第2 医療従事者・スタッフのための法律知識
- 医療現場における債権回収
- ▷診療報酬債権の回収
- ▷医療報酬の回収方法を確立しよう
- ▷未収金対策で上手な弁護士の利用方法
- ▷法的手続きの進め方
- ▷未回収のパターンと予防的対策
- 販売促進・広告
- 情報・データ
- コンプライアンス
-
事業承継
- 事業承継
- 認知症が招く法的トラブル その1
- 認知症が招く法的トラブル その2
- 認知症が招く法的トラブル その3
- 特別受益・・・相続の現場で現実に起こっている熾烈な問題とは!(その1)
- 特別受益・・・相続の現場で現実に起こっている熾烈な問題とは!(その2)
- 終末を考える際の対策
- 高齢化社会ニッポン。お嫁さんを守ることは大きな社会問題だ!
- 認知症患者が他人に損害を負わせたら、 家族はどんな責任を負うのか!?
- 遺産の預貯金は親の死亡後すぐに払い戻せるの?
- 遺留分対策ってどうやってやるの!?
- 会社に多額の連帯保証があって事業承継に二の足を踏んでしまうときは!?
- 思い込みは本当に危険! 悲惨な末期を辿ることになる!
- 子供への株式の譲渡
- 子供への土地の譲渡
- 遺言の作成
- 社長と認知症
-
学校問題
- 学校の法律問題
- 湊総合法律事務所の取組について
- 【解決事例】問題教員に対する解雇
- 【解決事例】職員の業務委託への切替
- 【解決事例】学校職員の定年問題について
- 【解決事例】改正労働契約法18条の施行に伴う規則整備
- 【解決事例】学内の不祥事への対応
- 【解決事例】教師のうつ発症に対する対策
- 内部だけで問題解決を図ることの危険性
- いじめ・体罰についての法律問題
- 給食費の滞納に関して
- 保護者からの損害賠償請求・謝罪文請求等
- ハラスメントに伴う法的責任
- 学校・保護者間のトラブル
- 学校事故の意味
- 部活動中の事故
- 学校の設備に起因する事故
- いじめへの対応
- 教職員の病気休暇・休職処分
- 教職員に対する借金督促の電話の問題
- 遅刻・忘れ物が多い
- 教職員の異性問題
- 教職員の飲酒運転に対する処遇
- 教職員によるセクハラ 意味
- セクハラと性別
- パワハラの意味
- 懲戒処分の可否・注意点
- 懲戒処分の前提となる事実調査の留意点
- 懲戒処分の可否・注意点-具体例に従って
- 顧問弁護士への相談
- 懲戒処分検討中の辞表提出
- 懲戒事由から長期間が経過した場合
- 教師による体罰
- FC契約・トラブル
- 競業避止
- 控訴審
- 下請法
-
債権回収
- <債権回収 総論>
- 弁護士による債権回収
- 債権回収を弁護士に依頼するメリット
- 湊総合法律事務所の債権回収の特長
- <債権回収 契約締結時について>
- 未収金にならないための予防方法
- 相手方が契約書を提示してきた場合
- 契約書作成時の注意点
- 担保権の設定
- 信用調査の必要性及び方法
- <債権回収段階について>
- 関係を悪化させずに回収する
- 売掛金の支払いが滞ってきた場合
- 債権回収の手段と手続きの流れ(取引先の支払いが停止した時)
- 内容証明郵便
- 代物弁済とは?弁護士が解説
- 担保権の実行
- 保証人から回収する
- 民事調停手続
- 支払督促手続
- 仮差押手続
- 訴訟手続(通常訴訟手続)
- 少額訴訟による債権回収
- 強制執行手続
- <債権回収の解決事例>
- 【解決事例】内容証明郵便にて未収金を600万円回収した事例(機械部品製造業)
- 【解決事例】動産売買先取特権を行使して債権を回収した事例(文具等製造販売業)
- 【解決事例】民事調停手続により話し合いに応じない両者が合意した事例(ホームページ制作会社)
- 【解決事例】支払督促手続によりサービス金額を全額回収した事例(インターネットサービス会社)
- 【解決事例】仮差押手続きにより売掛金全額を保全した事例(家具製造メーカー)
- 【解決事例】訴訟手続(通常訴訟手続)により売買代金800万円を回収した事例(商品の売買)
- 【解決事例】強制執行手続により貸金債権500万円を回収した事例(知人への貸付け)
- <債権回収 取引先が倒産した場合について>
- 取引先倒産の場合の債権回収
- 取引先が破産手続を開始
- 取引先が民事再生手続を開始
- 取引先が会社更生手続を開始
- 企業再生
- 知的財産
- 会社法
ご相談のご予約はこちらから



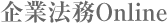
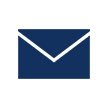 でのお問い合わせは
でのお問い合わせは