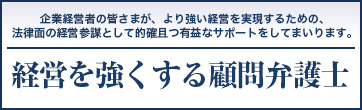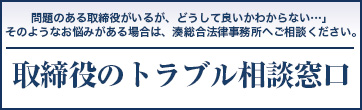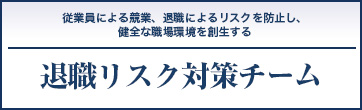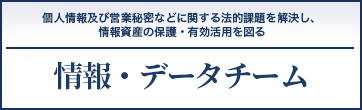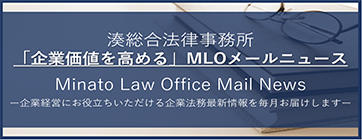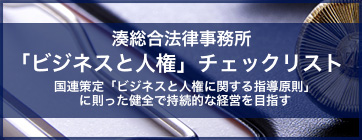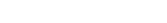動産売買先取特権
タイトル..
動産売買先取特権
動産(不動産以外の物)を販売したのに代金を支払ってもらえないときは、「動産売買先取特権」を行使することにより売買代金債権を回収することが可能です。
以下では、「動産売買先取特権」について、説明をします。
1.「動産売買先取特権」とは
2.「動産売買先取特権」が活躍する場面
3.「動産売買先取特権」の行使による債権の回収方法
1.「動産売買先取特権」とは
まず、「先取特権(さきどりとっけん)」とは、法律に定められた一定の債権を有する者が、一定の財産から、他の債権者に優先して弁済を受けることができる権利のことです(民法303条)。
先取特権は、「法定担保物権」であり、当事者間の合意がなくとも、法律により当然に付与される権利です。
この先取特権のうち、「動産売買先取特権」とは、動産を売却した者が、その動産の代金と利息から、他の債権者に優先して弁済を受けることができる権利のことです(民法311条5号、321条)。
例えば、ある動産売買の売主は、買主が売買代金を支払わないときに、その販売した動産(商品)を競売に付し、その換価金から優先的に売買代金債権を回収する権利を有することになります。
売買代金債権のような債権については、「債権者平等の原則」があり、債務者が全財産をもってしても全ての債権の支払いをすることができないという場合には、各債権者は、債務者の財産から、自己の債権額に応じて案分された金額の分配を受けるのが原則です。
「動産売買先取特権」を行使すると、かかる債権者平等の原則の枠外で、他の債権者に優先して債権を回収することが可能となります。
このような強い権利が動産売買の売主に付与されている理由については、売主がその動産を販売したからこそ、その動産が買主の財産となっているのであり、その動産の換価金に限っては、他の債権者に優先して売主が弁済を受けることを認めた方が、債権者間の実質的な公平を確保することになるため、とされています。
2.「動産売買先取特権」が活躍する場面
動産を売買する場合に、売主が売買代金債権を確保する手段としては、動産売買先取特権以外にも、以下のようなものが考えられます。
売買代金を先払いとする、所有権留保をする、買戻特約をつける、
保証金を預託させる、連帯保証人をとる、その動産に譲渡担保権を設定する、
買主や第三者の財産に抵当権を設定する、等
しかし、上記の手段は、いずれも、買主や連帯保証人等の同意なく行うことができないところ、売買契約の締結の際に買主等からかかる同意を得ることは、当事者間の力関係から難しい場合も多いと思われます。
また、買主が代金を支払えない状況に陥った後に抵当権などの設定をする行為については、他の債権者を害する行為であるとして、他の債権者から詐害行為取消請求(民法424条1項、424条の3第1項))をされたり、買主が破産手続開始申立てをした場合には破産管財人から否認権(破産法160条)を行使されたりする場合もあります。
そのため、上記の手段は、事前に買主等の同意を得て準備をしておかなければ使えない手段ということになります。
動産の売買において、事前に上記のような手段の準備をしていなかった場合に、売主が売買代金債権を確保するために使える権利が、法定担保物権である動産売買先取特権です。
動産売買先取特権は、破産手続において「別除権」として扱われますので(破産法2条9項)、債務者である買主が破産手続開始申立てをしても、破産手続とは別個に行使することが可能です。
なお、買主が売買代金を支払わない場合には、売買契約を解除して商品の返還を求めることも考えられますが、返還は、買主の同意を得て行う必要がある点には注意が必要です。
買主の同意を得ないまま、買主の事業所等に立ち入って商品を回収することは、「自力救済」に該当し、許されませんし、建造物侵入罪(刑法130条)や窃盗罪(刑法235条)にも該当することになります。
もし、買主が商品の返還に同意しない場合には、訴訟提起したうえで強制執行により返還を実現することが必要になりますので、買主が返還に同意しそうにないケースにおいては、動産売買先取特権を行使することを積極的に検討すべきと考えられます。
3.「動産売買先取特権」の行使による債権の回収方法
動産売買先取特権の対象となる動産が買主のもとにあるか、すでに転売されているのかによって、必要な法的手続が異なります。
(a)対象となる動産が買主の手元にある場合は、動産競売を行う。
販売した動産が買主の手元にある場合には、裁判所に対して、動産売買先取特権の存在を証する文書を提出して、動産競売の開始許可申立てを行います(民事執行法190条2項)。
裁判所が動産競売の開始を許可した後、債権者である売主は、執行官にその許可決定書の謄本を提出します。そして、その許可の決定が債務者である買主に送達されると、動産競売が開始されます(民事執行法190条1項3号)。
動産競売においては、裁判所の執行官が、対象となる動産が保管されている買主の倉庫などへ立ち入り、差押えをします(民事執行法192条・123条1項、2項)。
そして、その動産を競売し、売主は競売代金から配当を受けることになります(民事執行法192条・139条)。
(b)対象となる動産が転売された場合は、転売代金債権を差し押さえる(物上代位)。
販売した動産が第三者に転売された場合には、(a)の方法は使えません。
この場合は、買主の第三者に対する転売代金債権を差し押さえることによって、他の債権者に優先して弁済を受けることができます(民法304条)。このような動産売買先取特権の効力を「物上代位」といいます。
手続としては、裁判所に対して、動産売買先取特権の存在を証する文書を提出して、債権差押命令申立てを行います(民事執行法193条1項)。
差押命令が発令されれば、その後、転売先から直接代金を回収することが可能となります(民事執行法193条2項・155条)。
なお、動産売買先取特権に基づく物上代位による転売代金債権の差押えは、転売先から転売代金が支払われた後では行うことができません(民法304条1項ただし書)ので、早期に実施する必要があります。
動産売買先取特権は、買主の同意なく発生する強力な権利です。
しかし、実際に行使しようとすると、買主の保有している多数の動産の中から売主が販売した商品を特定することが困難なことが多くありますし、また、物上代位の場合は転売代金の支払前に差押えを行う必要があり、ケースによっては予め転売代金債権を仮差押えしておくことが必要となるなど、実際に行使する場面では難しい判断が要求される権利であるともいえます。
動産売買取引を行う際には、日頃から、契約書・発注書・受注書・契約書・納品書等の書類をきちんと備え、契約関係や納品したことの証拠を揃えておくことが肝要です
動産売買先取特権の行使をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
-300x72.png)
債権回収の関連ページ
取扱分野
ご相談のご予約はこちらから



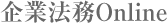
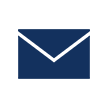 でのお問い合わせは
でのお問い合わせは