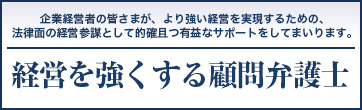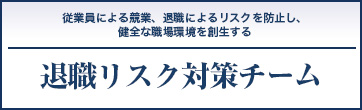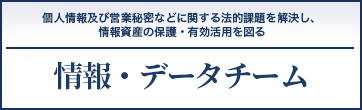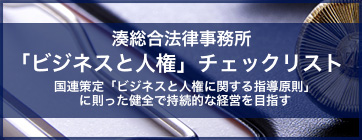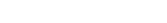労働条件の不利益変更
タイトル..
労働条件の不利益変更
人事処遇制度の見直しや人件費の削減は、企業の人事担当者にとって重要な課題です。
しかし、法的には、労働条件を従業員に不利益に変更することは限定された場合にしか認められず、これを知らずに安易に労働条件の切下げを行ってしまうと、大きな問題に発展するおそれがあります。
以下、不利益変更を行おうとする際の留意点とその対策について説明します。
1 労働条件の不利益変更とは
労働条件とは、労働契約関係における労働者の待遇の一切をいいます。賃金や労働時間、休暇などだけではなく、災害補償、福利厚生などに関する諸条件も含まれます。
労働条件は、会社と従業員との間に既に成立した労働契約の内容ですから、会社が、理由もなく一方的に従業員の不利益に変更することはできません。
理由のない一方的な不利益変更は無効となりますので、従業員から、変更前の労働条件に基づいた請求が認められることになります。
2 不利益変更の基本的な手続の進め方
有効に労働条件を変更する方法としては、以下の方法があります。
・従業員ごとに合意を得る(労働契約法第9条)
・労働組合との間で労働協約を締結する
・労働契約法第10条の定めに従って就業規則の変更(同法に定める制限があります)
労働契約も契約ですから、原則的には契約当事者(契約当事者が所属する労働組合を含む)の合意によってその内容を変更することができます。そこで、①・②のように労働条件の変更について対象となる従業員等の合意が得られれば、原則として不利益変更も有効となります。したがって、会社としては、まず従業員等に対し十分な説明・協議を行い、合意を得ることを目指すべきです。
合意が得られない場合は、③のように就業規則を変更することにより労働条件の変更を行うしかありません。ただし、この場合は当該変更に合理性が認められる場合のみ不利益変更に効力が生じます。
3 個別的合意と労働協約の締結について
(1)個別的合意による変更
合意により有効に労働条件を変更する具体的方法として、まず、変更の適用を受ける従業員全員との間で個別に合意を得る方法があります。
なお、個別の合意を得た場合でも、従来の労働条件について定める就業規則をそのまま放置すると、労働契約法12条「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。」との規定により、当該変更に関する合意は無効となってしまいます。
個別の合意を得た際は、変更した部分の就業規則を必ず改訂するよう留意しましょう。
(2)労働協約の締結による変更
社内に労働組合がある場合、組合との間で変更措置に合意する労働協約を締結すれば、当該組合の組合員については、原則として個別の同意なくして労働条件の変更を行うことができます。
労働条件の変更の対象となる従業員が多数にわたる場合には、個別的合意に比べ、その処理に費やすエネルギーを大幅に削減することができます。
労働協約締結の際には以下のような注意点があります。
①効力が及ぶのは原則として組合員のみ
組合との労働協約によって不利益変更が有効となるのは、基本的にはあくまでも「組合員」との間であり、非組合員には影響しません。よって、非組合員に効力を及ぼすには当該非組合員の個別の合意を得ることが必要です。
もっとも、例外的に、組合の組織率が当該事業場の4分の3以上を占める場合には、組合との間に成立した労働協約は、当該事業場に使用される他の同種の労働者にも適用されるものとされています(労働組合法17条)。但し、当該変更が社内の他の少数労働組合の組合員にも適用されるか否かについては、裁判例で判断が分かれていますので注意が必要です。
②組合員でも効力が及ばない場合がある
労働協約が締結された場合でも、特定又は一部の組合員を殊更に不利益に扱うことを目的として締結されたなど、労働組合の目的を逸脱して締結された場合は、労働協約の効力は否定されます。(最高裁判所平成9年3月27日判決)
したがって、一部の組合員が犠牲となるような変更については、当該組合員の意見を聴取して不利益を緩和するよう努めた上で労働協約を締結すべきです。
4 従業員への上手な説明の仕方
個別的合意を得る際にも、労働協約を締結する際にも、従業員や労働組合に対して十分な説明を行い、理解を得ることが重要です。
当該変更の具体的内容を正確に伝えることはもちろん、会社の経営状況の悪化など当該変更が必要である実質的理由について特に詳しく説明し、理解を得るよう心がけましょう。また、従業員への不利益が大きい変更の場合は、代償措置を用意し、これを提案・協議する形で交渉を進めるのが良いでしょう。
従業員や労働組合の抵抗が強いほど威圧的な態度に出たり解雇をちらつかせたりするケースがありますが、このような方法で合意を得ても、この合意は無効となるリスクを孕むものです。また、合意した従業員が、会社提案の労働条件に合意しなければ従業員としての地位を失うと誤信してこれに合意したと主張した場合、裁判所において当該合意は無効と判断される可能性があります。
従業員が「自由な意思」で合意したか否かの判断に関しては、最高裁判決平成28年2月19日が参考になります。
同判例は「就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無については、当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけでなく、当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度、労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様、当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして、当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも、判断されるべきものと解するのが相当である」と判示しています。
したがって、合意書に署名・捺印があれば足りるということにはなりませんので、注意が必要です。
5 合意書の必要性と効力
(1)労働協約の場合
労働組合との間で合意に至った場合は労働協約を締結しますが、これは書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによって初めてその効力を生じます(労働組合法14条)。合意書作成が効力発生の要件となっていますので、忘れずに書面を作成しましょう。
(2)個別的合意の場合
労働協約の場合と異なり、各従業員との個別的合意の場合には、特段、書面によることとする法律上の要請はありません。
しかし、当該従業員が「そのような合意はしていない」と主張した場合、会社側が従業員の同意の存在を証明することができなければ、合意はなかったと判断されてしまいます。したがって、個別的合意の場合にも必ず従業員の同意書を作成する必要があります。
また、個別的合意の場合には無効等を主張されるリスクも高いことから、同意書の中に十分な説明を受けこれを理解したことを盛り込むとよいでしょう。
6 就業規則の変更による場合
個別的合意や労働協約による合意が得られない場合には、まず、本当に当該変更が会社にとって必要不可欠なものか再度検討すべきです。なぜなら、これを強行した場合、無効と判断されるリスクは格段に高くなるからです。
再検討した結果、やはり実施せざるを得ないものである場合には、就業規則を変更することにより労働条件の変更を行います。
就業規則の変更の際には、以下の事項に留意が必要です。
(1)手続面での注意事項
労働基準法上、就業規則の作成・変更には複数の手続的規定が定められていますのでこれを遵守しましょう。
(2)内容面での注意事項
①法令・労働協約に違反していないか
就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならないとされています(労働契約法13条)。そこで、変更後の内容が法令や労働協約に反するものとなっていないか確認が必要です。
予定していた変更後の就業規則と労働協約とが反するときは、当該労働協約に有効期間の定めのある場合は労働協約の有効期間の満了を待って就業規則の変更を行い、有効期間の定めのない場合は労働協約を少なくとも90日前の文書による予告をもって解約し(労働組合法15条3項4項)、その後就業規則の変更を行うこととなります。
②当該変更に合理性があるか
就業規則の変更は、それが労働者の受ける不利益の程度、労働条件変更の必要性、変更後の内容の相当性、労働組合等との交渉状況、その他の就業規則の変更の状況に照らして合理的なものであることが必要です(労働契約法10条)。
どのような場合に「合理性」があるかについては、「労働者の受ける不利益性」と「使用者側の変更の必要性」とが総合的に判断されています。
当該変更により労働者に与える不利益が大きければ大きいほど、変更に関して高度の必要性が求められ、また、代償措置を整備した等などの合理性を基礎付ける事情がなければ、当該変更は無効とされるおそれが高いと考えてよいでしょう。
7 就業規則による不利益変更のケース別のトラブル防止のポイント
(1)退職金の廃止、減額変更
賃金、退職金などの特に重要な権利、労働条件の不利益変更にあたっては、その合理性は特に厳しく判断され、「そのような不利益を労働者に法的に受任させることを許容できるだけの高度の必要性に基づいた合理性」がある場合に限り、労働者に対する拘束力を有するとされています(最高裁判所昭和63年2月16日判決)。
また、退職金算定の基礎となる就労期間を打ち止めとした事案の判例では、従業員に不利益を一方的に課すものであるにもかかわらず使用者はその代償となる労働条件を何ら提供しておらず、合理的なものとは言えないなどとして当該措置は無効と判示されています(最高裁判所昭和58年7月15日判決)。
このように、一方的な賃金の減額や退職金制度の廃止に関しては、会社側に高度の必要性が認められない限り合理性が認められることは困難です。
企業としては、従業員や労働組合に対し制度廃止の必要性を説明して、何とか合意を得た上で制度廃止を行うよう尽力し、それでもやむを得ない場合には少額の減額にとどめる、代償措置を講じるなどの不利益緩和に努めるべきといえます。
(2)通勤手当や食事手当の不支給又は減額
通勤手当や食事手当が「賃金」にあたるかどうかですが、賃金とは、「賃金、給料、手当、賞与その他の名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」とされています(労働基準法11条)。「労働の対償」とは、原則として、①任意的・恩恵的給付(慶弔見舞金等)、②福利厚生給付(貸金貸付等)、③企業設備・業務費(作業用品の購入費等)以外のものであると考えられています。
もっとも、一見上記①~③にあたるように見える場合でも、就業規則、給与規定等により、あらかじめ支給条件や支給義務が明らかにされている場合には、賃金に該当するとされることがあります。
通勤手当や食事手当については、③企業設備・業務費にはあたらず、また、企業において、何らかの社内規定により支給基準が定められていることが多いため、変更に際しては基本的に賃金の引下げと同様に合理性が求められます。
この点、通勤手当、扶養手当、住宅手当を実費金額支給から上限を設定して減額した事案につき、人件費削減の必要性は肯定できるが、手当の額は使用者にとっては大きな金額ではなく、人件費削減にはさほど貢献しない反面、労働者にとっては実費を含む上、少なくない金額であるなどとして、通勤手当等の減額を無効と判断した裁判例(大阪地方裁判所平成12年8月25日判決)もあります。
もっとも、多くの場合、諸手当の引下げは基本給の引下げに比べて従業員の不利益が少ないと考えられますので、引下げ幅が少額で、一時的な引下げにとどまるなど合理性を基礎づける事情が多くあれば、従業員等の同意なくしてこれを行うことも可能であると考えられます。
(3)制服を会社支給から従業員の自前もしくは一部負担への変更
制服、作業服、作業用品の購入費用などは③企業設備・業務費にあたりますので、通常「賃金」には該当しません。
そこで、就業規則等に支給に関する定めがない場合には、従業員等の同意を得ずして会社支給から従業員の自前もしくは一部負担にすることも、より広く認められるでしょう。
(4)財形支援(利子補給など)の廃止もしくは縮小
利子補給金等の財形支援は任意的・恩恵的給付の側面を有しますので、原則として賃金に該当しない場合が多いものと思われます。
よって、従業員の同意を得ずとも変更が認められやすいと考えられます。
8 不利益変更を強行した場合のリスクとデメリット
従業員との個別的合意や労働協約の締結を経ずに不利益変更を強行した場合、これに反発する従業員により当該不利益変更の無効を前提として変更前の地位に基づく請求を内容とする訴訟が提起されるおそれがあります。
当該不利益変更が無効と判断されて会社が敗訴した場合、無効と判断される程の不合理な労働条件を一方的に従業員に押しつけたと認識されることによる会社への不信感の増大や企業内の士気の低下、ブランド価値の悪化というリスクは計り知れません。労働条件の不利益変更をめぐる事件については、裁判所の判断が数多く示されていますが、これがこの分野に関する紛争の多さを物語っています。
したがって、実務的には、法的に有効か否かのみでなく、いかにして従業員の理解、納得を得た上で穏便に労働条件の変更を行えるかが重要なポイントとなります。会社 としては、組合、従業員の真意による合意を得ることを第一に考え、不利益変更を強行することはできる限り避けるべきでしょう。
お困りの方は湊総合法律事務所までご相談ください。
| <顧問弁護士について> 顧問弁護士が継続的に企業経営に関する法的なサポートをさせていただくことで、より効果的に法的トラブルを防止し、迅速かつ的確な問題解決を図ることが可能となります。 そのために私達の事務所では法律顧問契約を締結して対応させていただくことをお薦めしております。担当弁護士が貴社の状況を把握して、直接お会いして、あるいは電話、メール、Zoomなどの手段を適切に利用して、相談に臨機応変に対応させていただきます。 こうすることにより問題発生前に法的トラブルを防止し、 企業価値を高めることを可能としています。 法律顧問料はかかりますが、結果としてコストの削減にも繋がっていきます。 ▷顧問契約についての詳細はこちらに掲載しております。是非ご参照ください。 |
労務問題の関連ページ
- 労務問題
- 採用内定の取り消し
- 試用期間中の社員に問題があるとき
- 本採用を拒否するには
- 労働条件の不利益変更
- 育児休業(育休)復帰後の職務変更・賃金減額について
- 同一労働同一賃金の基礎知識とポイント
- セクハラ被害を申告されたら
- パタニティ・ハラスメント対策
- 自宅待機命令と賃金支払義務
- 起訴休職処分
- 解雇紛争の予防と対処
- 従業員を解雇できる場合とは
- 売上の減少に伴い整理解雇を行うには
- 解雇と退職勧奨
- 退職勧奨の進め方とポイント
- 退職勧奨の面談時における留意点
- 退職勧奨が違法となる場合
- 解雇の要件とは
- 有期労働者の無期契約への転換
- 退職後の競業避止義務について
- フリーランスと競業避止義務
- 労務問題に関する当事務所の解決事例
- 当事務所のIT業界労務特化コンサルティング
取扱分野
ご相談のご予約はこちらから



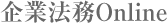
-300x72.png)

.png)
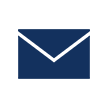 でのお問い合わせは
でのお問い合わせは