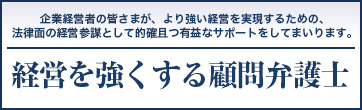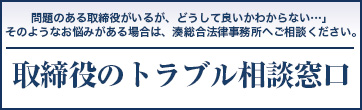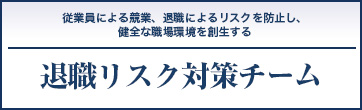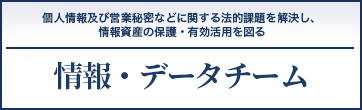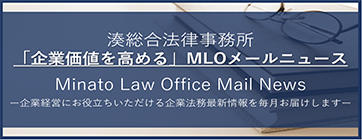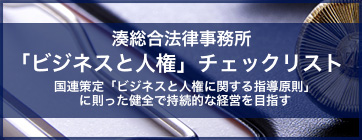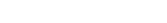起訴休職処分
タイトル..
起訴休職処分
Q.当社の従業員Aが、通勤中の電車内で痴漢を行ったとして逮捕・勾留され、起訴されました。
Aは「やっていない」と犯行を否認して争っており、現在は保釈されて裁判の最中です。
当社の就業規則には「従業員が起訴された場合には休職を命ずる」という起訴休職に関する規定があります。
犯行を否認して、また保釈されている場合でも、起訴休職処分にしてもよいのでしょうか?
A.会社の就業規則に起訴休職処分の定めがあるだけで直ちに処分を行うことには問題があります。
当該従業員の地位・職務・起訴事実の内容・勾留の有無その他具体的な事情を考慮して、当該従業員を就労させることによって会社の対外的信用の失墜・職場秩序の維持に障害が生じるおそれの有無、労働力の継続的な給付や企業活動の円滑な遂行に支障が生じるか否か十分に検討した上で、処分するか否かを決定する必要があります。
起訴休職制度
起訴休職とは、労働者が刑事事件で起訴された場合に、刑事裁判の確定まで一時的に労働者を休職させる制度のことをいいます。
従業員が起訴された場合、起訴事実の種類・態様、その従業員の企業内の地位・担当職務によっては、企業の対外的信用が失墜し、職場秩序の維持に障害が生じる場合があり得ます。
また、起訴された従業員は、原則として公判期日に出頭する義務を負い、場合によっては勾留されることもあるので、その従業員が仕事に就けないことによって企業活動の円滑な遂行に支障が生じることもあり得ます。
そのような事態を避けるために、就業規則に「刑事事件で起訴された者は、その事件が裁判所に係属する間は休職処分とする」といった起訴休職の規定が設けられていることがあります。
起訴休職を命ずることの有効性
就業規則に起訴休職の定めがある場合であっても、裁判実務では、起訴の事実だけで当然に起訴休職が有効となるものではありません。
起訴後も勾留されたままの身柄拘束状態であれば、労務の提供ができない状態にあるため、休職命令を出さざるを得ないと思われますが、当該従業員が起訴後保釈されている場合には会社としては慎重な対応が必要です。
刑事事件になっていても、有罪判決が確定するまでは被疑者・被告人には「無罪の推定」が働きますので、起訴休職が有効となるためには、起訴されたという事実のほか、以下のような事情が認められることが必要であると考えられます(東京地裁平成11・2・15、東京地裁S61・9・29等参照)。
① 職務の性質、公訴事実の内容、身柄拘束の有無など諸般の事情に照らし、起訴された従業員が引き続き就労することにより、会社の対外的信用が失墜し、又は職場秩序の維持に障害が生ずるおそれがある場合
② 当該従業員の労務の継続的な給付や企業活動の円滑な遂行に障害が生ずるおそれがある場合
③ 起訴事実が確定的に認められたときに行われる可能性がある懲戒処分の内容と比較して明らかに均衡を欠く場合でないこと
具体的にどのような事情があれは上記の要件を満たすかは、個々の事案によって異なりますが、①については、従業員Aの会社での地位・業務内容、事件が業務に関係して起こったものか否か、信用の失墜が従業員Aの業務と時間・場所・内容と関係があるか否か、起訴事実自体が軽微なものといえるか、社会的な影響力の大小、マスコミ等の取材による混乱の有無、顧客先に対する敵視行為の有無等が問題となります。
②については、身柄拘束の有無、在宅起訴の場合でも従業員Aが公判にどれだけの時間を割かねばならないか等が問題になるといえます。
本事例のように従業員が起訴後保釈されている場合、刑事裁判の公判期日には会社を欠勤しなければならないとしても、事前に届け出て有給休暇を取るなどして裁判に出頭することも可能ですから、起訴されたことが直ちに労働力の継続的な給付や企業活動の円滑な遂行に支障をもたらすものではないといえます。
裁判例(東京地裁平成15・5・23)は、本事例と同様に、電車内での痴漢行為によって起訴された従業員に対する休職処分が問題となった事案ですが、保釈されていて、保釈取消の可能性も低かったこと、女性のほとんどいない職場・職種に対する配置転換をすることも充分に可能であったにもかかわらずかかる措置を講じなかったこと等を理由に、休職処分を違法・無効としました。
他方で、別の裁判例(東京地裁S62・9・22)では、業務上横領事件で起訴休職された非営利法人の従業員について、起訴後に保釈されていることから労働力給付という点では問題がないものの、非営利法人であること、全国紙で大々的に報道されるなどの騒動があったこと等から企業の信用失墜という点が重視され、休職処分を適法・有効としました。
以上のように、起訴休職処分をするか否かについては、上記の要件に該当するか否かを具体的事情に即して、慎重に判断する必要があります。
なお、具体的事情に基づいて起訴休職が適法だと評価される場合には、その後無罪判決が確定したとしても、遡って起訴休職が違法・不当とされることはありません。
起訴休職は、起訴されたこと自体を要件として、起訴事実の内容と当該従業員の地位・担当職務によっては、職務にそのまま従事させることが対外信用、職場秩序の維持の上で支障を生じ、あるいは公判期日への出頭等のため労務提供にも支障を生ずる場合があることから行われるものであり、起訴された事実について有罪となることを前提とするものでないからです。
お困りの方は湊総合法律事務所までご相談ください。
| <顧問弁護士について> 顧問弁護士が継続的に企業経営に関する法的なサポートをさせていただくことで、より効果的に法的トラブルを防止し、迅速かつ的確な問題解決を図ることが可能となります。 そのために私達の事務所では法律顧問契約を締結して対応させていただくことをお薦めしております。担当弁護士が貴社の状況を把握して、直接お会いして、あるいは電話、メール、Zoomなどの手段を適切に利用して、相談に臨機応変に対応させていただきます。 こうすることにより問題発生前に法的トラブルを防止し、 企業価値を高めることを可能としています。 法律顧問料はかかりますが、結果としてコストの削減にも繋がっていきます。 ▷顧問契約についての詳細はこちらに掲載しております。是非ご参照ください。 |
労務問題の関連ページ
- 労務問題
- 採用内定の取り消し
- 試用期間中の社員に問題があるとき
- 本採用を拒否するには
- 労働条件の不利益変更
- 育児休業(育休)復帰後の職務変更・賃金減額について
- 同一労働同一賃金の基礎知識とポイント
- セクハラ被害を申告されたら
- パタニティ・ハラスメント対策
- 自宅待機命令と賃金支払義務
- 起訴休職処分
- 解雇紛争の予防と対処
- 従業員を解雇できる場合とは
- 売上の減少に伴い整理解雇を行うには
- 解雇と退職勧奨
- 退職勧奨の進め方とポイント
- 退職勧奨の面談時における留意点
- 退職勧奨が違法となる場合
- 解雇の要件とは
- 有期労働者の無期契約への転換
- 退職後の競業避止義務について
- フリーランスと競業避止義務
- 労務問題に関する当事務所の解決事例
- 当事務所のIT業界労務特化コンサルティング
取扱分野
ご相談のご予約はこちらから



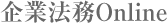
-300x72.png)
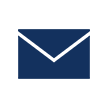 でのお問い合わせは
でのお問い合わせは