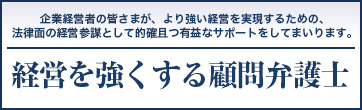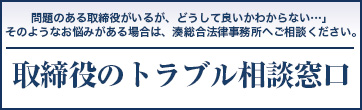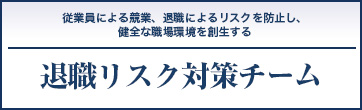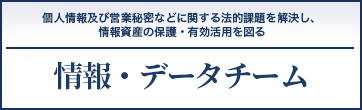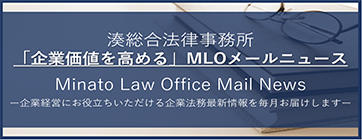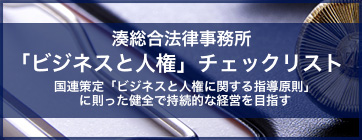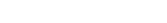有期労働者の無期契約への転換
タイトル..
有期労働者の無期契約への転換
(1) 無期転換ルールの概要
労働契約法18条に定められた無期転換ルールとはどんな制度ですか。
有期労働契約(期間が定められた労働契約)は、契約期間が満了したとき、契約が更新されて雇用関係が継続することもあれば、契約が更新されないで雇用関係が終了(「雇止め」といいます。)することもあります。
つまり、有期契約労働者にとっては、雇止めを受けてしまう不安があることから、例えば、本来であれば取得が許されているはずの年次有給休暇をきちんと取得しないなど、正当な権利行使が事実上抑制されてきたという実情がありました。こうした実情を踏まえて、労働契約法18条が平成24年に改正されました。
労働契約法18条は、同一の使用者との間で、有期労働契約期間が通算して5年を超えて反復更新された場合、その労働者の申込みによって無期労働契約へと転換することを認めたものです。lこれを無期転換ルールといいます。
(2) 「同一の使用者」の意義
「同一の使用者」の意義をお教えください。労働契約法18条は、「同一の使用者との間で」と規定していますが、親会社で有期労働契約者として3年間働き、その後、子会社へ出向して有期労働契約者として3年間働いたという場合には、「同一の使用者」に当たらないのでしょうか。
「同一の使用者」に当たるか否かは、法人ないし事業主単位で判断されると解釈されています。そうすると、親子関係にある会社であっても法人格としては別ですから、「同一の使用者」に当たらないというのが原則です。
しかしながら、別法人であるとはいえ、資本的に見れば実質的には同一の会社といえるような場合には、「同一の使用者」に当たると判断される可能性を否定することはできません。
使用者である法人ないし事業主が、就業実態が変わらないにもかかわらず、労働契約法18条に基づく無期転換を免れる目的で、形式上使用者を他の法人等に変えて別の契約関係を作出した場合、それは脱法行為として、同一の使用者との労働契約が継続していることとなります。
なお、法人が同一であるならば、事務所や職種、勤務条件、待遇が変わったとしても、「同一の使用者」の下で働いたことに変わりはありません。
(3) 「通算契約期間」
ア プロジェクトの延期と通算契約期間
あるプロジェクトのために労働者を5年間の有期契約で雇用したところ、地震が発生して業務が停止してしまい、プロジェクトの完成が延期したため、やむなくこの労働者との契約を1年間だけ更新しました。この場合であっても、無期労働契約への転換権は認められますか。
労働契約法18条は、①有期労働契約を2回以上締結し、かつ、②通算の契約期間が5年を超える場合に、無期労働契約への転換を申し込むことができると規定しています。
天災のように、使用者側に責任が全くない事情による延長であっても「通算契約期間」に算入されると考えられています。今回の場合、この労働者は、更新により通算して6年間働いているため、「通算契約期間」は5年を超えるので、転換権が認められます。
企業においては、特定のプロジェクトのためだけに労働者を雇用するということがあります。その場合に大切なことは、①当初の有期労働契約を締結する際に、②業務が今回のプロジェクトのみに限定されることを契約書や就業規則に明記し、かつ、その内容を労働者に確認させて合意を得ておくことです。
そうすることによって、労働者側に予測可能性を与えることができ、後々の紛争を防ぐことができます。
横浜地裁川崎支部判決令和3年3月30日は、有期雇用契約の中に、最初の雇用契約開始日から通算して5年を超えて更新することはない旨の条項が付されていて、会社が当該条項に基づき当初の雇用契約から5年の期間満了を以て原告を雇止めしたところ、労働者が、当該条項は労働契約法18条の無期転換申込権を回避しようとするもので無効であると主張した事案です。判決では、労働者において未だ更新に対する合理的期待が形成される以前の段階である雇用契約締結当初から、更新上限があることが明確に示され、労働者もそれを認識の上本件契約を締結していたことを指摘し、労働者の上記主張を斥けました。
イ 役職の変更と通算契約期間
当社には、2年契約の非常勤職員として4年間、1年契約の常勤職員として3年間勤務した者がいます。この者の通算契約期間は何年間と計算されますか。
非常勤として4年間、常勤として3年間ですから、各々の契約期間を独立させて見ると、5年を超えません。しかしながら、通算契約期間を計算する上では、職務内容や役職名の違いは考慮されませんので、非常勤としての契約期間も、常勤としての契約期間も、ともに「通算契約期間」としてカウントされます。
したがって、この労働者の通算契約期間は、非常勤としての4年間と、常勤としての3年間を合計した7年間と計算されます。また、ずっと非常勤として勤務し、その通算した契約期間が5年を超えた場合であっても、「通算契約期間」が5年を超えたものとして計算されます。
ウ 通算契約期間と空白期間
当社には、1年契約を2回更新した後に退職した職員がいます。本校では、この職員を、退職から1年後に2年契約で雇用することとし、先日、この契約を1回更新しました。この職員の通算契約期間はどうなりますか。
一度退職した職員を再雇用した場合、前の契約期間と今回の契約期間との間に、幾らかの空白期間が生じます。この空白期間が6か月未満であれば、前の契約期間も「通算契約期間」に入りますが、空白期間が6か月以上となった場合には、前の契約期間はいわばリセットされて、「通算契約期間」に入らなくなります。
今回の職員について見ると、前の契約期間(3年間)と、今回の契約期間(4年間)との間に、1年間の空白期間が生じていますので、前の契約期間(3年間)は「通算契約期間」に入りません。
したがって、この職員の「通算契約期間」は、今回の契約期間である4年間として計算されます。なお、この空白期間は、原則として6か月間継続していなければならず、細切れの空白期間を合算して6か月間とすることは、例外はあるものの、基本的には認められていませんので、注意しましょう。
エ 育児休業等と空白期間
育児休業や介護のための休業、研究のための休職も空白期間に当たりますか。
いわゆる「空白期間」は、雇用契約が終了している場合をいいますが、育児休業中や介護休業中、研究のための休職中は、雇用契約自体は維持されています。したがって、これらの期間は「空白期間」には当たらず、「通算契約期間」に算入されます。
(4) 転換権
ア 転換が認められる始期
令和3年4月1日付けで3年間の有期労働契約を締結し、令和6年4月1日付でこの契約を更新したとします。この場合、無期労働契約への転換権が発生するのは、最初の契約期間開始から5年を超えた令和8年4月1日ですか。
令和6年4月1日時点で3年間の有期労働契約を更新した場合、最初の3年間と合わせれば6年となり、通算契約期間は5年を超えることになります。この場合、転換権が発生するのは、5年を超えることとなる契約の開始時期、つまり、令和6年4月1日になります。
この事例を少し変えて、最初の契約期間も更新後の契約期間も2年半ずつだったとしましょう。その場合、令和8年3月31日時点では通算契約期間がちょうど5年であって、まだ5年を超えてはいません。そうすると、この労働者に転換権が発生するのは、更にこの契約を更新した令和8年4月1日時点となります。
イ 兼業
甲は、A社において正規職員として雇用される一方、B社において有期労働契約者(非常勤講師)として雇用されています。
A社においては、他の使用者の下で働いている労働者との無期労働契約を締結することを就業規則で禁じています。この場合、甲は、B社において無期労働契約への転換権が認められますか。
A社の就業規則はA社での問題であって、B社における転換権には関係がありません。B社での雇用契約が更新されて「通算契約期間」が5年を超えたならば、B社における転換権は認められます。
ウ 無期労働契約転換権の放棄
私は、ある会社に勤務する者です。私が現在の会社に雇用されるに当たり、会社側から求められて、「私は、通算契約期間が5年を超えた場合であっても、無期労働契約への転換権を行使しません。」といった内容の念書に署名しました。私は、転換権を行使することはできませんか。
前掲横浜地裁川崎支部判決令和3年3月30日によれば、労働者に対し、有期雇用契約を締結する段階で5年を超えては更新がないことを説明して更新への期待を喪失させておけば、転換権を放棄させることを可能とする余地があります。
なお、その説明が最初の雇用契約締結時になく、契約更新時に転換権不行使の条件を付した契約をした場合、既に契約更新への合理的期待を有している労働者の自由意思を阻害するものとして、この条件は無効となります。
エ 転換権行使期限の定め
就業規則に「無期労働契約への転換権行使は、契約期間満了の30日前までに行うこと。」という定めがありますが、この定めに反し、例えば、契約期間満了の前日に転換権を行使した場合、転換は認められますか。
法律上、いつまでに行使しなければならないという制約がありません。したがって、期間満了の前日であっても転換権行使は認められると考えられています。
オ 転換権行使の効果-労働条件の変更
ある会社に勤務する非常勤職員が、労働契約法18条に基づいて無期労働契約への転換を申し込み、これが認められた場合、この職員は常勤職員となりますか。
転換が認められた場合の労働条件は、転換前と「同一の労働条件」(労働契約法18条1項)ですので、非常勤職員だった者が転換により自動的に常勤職員となるわけではありません。従前の労働条件を変更するためには、その旨の契約を別途締結する必要があります。
カ 転換権行使の効果-定年の扱い
有期労働契約上、定年を設けていなかった場合に、労働契約法18条に基づいて転換が認められ、労働条件が従前と同じとなった場合、定年と労働契約期間との関係はどうなりますか。
従前と同じ条件、つまり定年の定めのない条件で契約が成立しているため、定年になっても無期労働契約は終了しないと考えられています。
(もっとも、このように考えると、その労働者が死亡するまで契約関係が継続することになりかねず、非現実的です。こうした立法・解釈は将来的には見直される可能性があるでしょう。)。
また、就業規則で65歳を定年としている場合において、既に65歳に達した有期労働契約者が無期労働契約への転換権を行使したとき、定年を理由として転換を認めないとか、契約期間終了ということにはできないと考えられています。
そこで、こうした事態を避けるためには、「転換権を行使した場合には定年を○歳とする。」といった取決め・合意をしておくことが必要です。
キ 転換権の不行使
有期労働契約を反復更新して通算期間が5年間を超えた場合、自動的に無期労働契約へと移行しますか。
無期労働契約に転換するためには、転換権を取得した上、転換を申し込む必要があります。したがって、申込がない場合にまで自動的に無期労働契約へと移行することはありません。
(5) 労働契約法19条の概要
企業側として、無期労働契約への転換を防ぎたい場合には、通算契約期間が5年ちょうどになった時点で、その労働者との契約を打ち切れば(雇止め)よいのでしょうか。
確かに、既に説明したとおり、5年を超えて有期労働契約が更新されると労働契約法18条が適用されますので、有期労働契約を更新したとしても、通算契約期間を5年以内に収めることができれば、同条は適用されないこととなります。
ただし、むやみに雇止めをしようとすると、労働契約法19条の規制に抵触する場合があります。というのも、同条によると、有期労働契約を何度も更新し、
①無期労働契約と実質的に同視することができる状況にある場合。
②その労働者が「今後もずっと契約が更新されるだろう。」と合理的に期待するような状況にある場合。
には、その労働者に対する雇止めが制約されるのです。
ですから、例えば、更新回数の上限が就業規則等に明記されていないとか、明記されてはいるものの、実際には例外的な運用が行われている、あるいは、労働者に今後の更新を期待させるような言動をしてしまうといった場合には、労働契約法19条によって雇止めが認められない可能性が出てきます。
お困りの方は湊総合法律事務所までご相談ください。
| <顧問弁護士について> 顧問弁護士が継続的に企業経営に関する法的なサポートをさせていただくことで、より効果的に法的トラブルを防止し、迅速かつ的確な問題解決を図ることが可能となります。 そのために私達の事務所では法律顧問契約を締結して対応させていただくことをお薦めしております。担当弁護士が貴社の状況を把握して、直接お会いして、あるいは電話、メール、Zoomなどの手段を適切に利用して、相談に臨機応変に対応させていただきます。 こうすることにより問題発生前に法的トラブルを防止し、 企業価値を高めることを可能としています。 法律顧問料はかかりますが、結果としてコストの削減にも繋がっていきます。 ▷顧問契約についての詳細はこちらに掲載しております。是非ご参照ください。 |
労務問題の関連ページ
- 労務問題
- 採用内定の取り消し
- 試用期間中の社員に問題があるとき
- 本採用を拒否するには
- 労働条件の不利益変更
- 育児休業(育休)復帰後の職務変更・賃金減額について
- 同一労働同一賃金の基礎知識とポイント
- セクハラ被害を申告されたら
- パタニティ・ハラスメント対策
- 自宅待機命令と賃金支払義務
- 起訴休職処分
- 解雇紛争の予防と対処
- 従業員を解雇できる場合とは
- 売上の減少に伴い整理解雇を行うには
- 解雇と退職勧奨
- 退職勧奨の進め方とポイント
- 退職勧奨の面談時における留意点
- 退職勧奨が違法となる場合
- 解雇の要件とは
- 有期労働者の無期契約への転換
- 退職後の競業避止義務について
- フリーランスと競業避止義務
- 労務問題に関する当事務所の解決事例
- 当事務所のIT業界労務特化コンサルティング
取扱分野
ご相談のご予約はこちらから



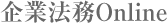
-300x72.png)

.png)
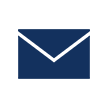 でのお問い合わせは
でのお問い合わせは