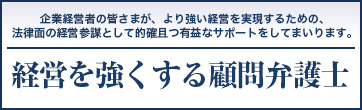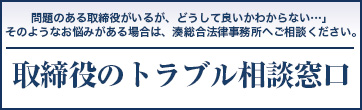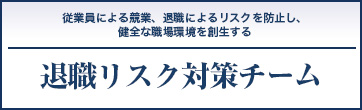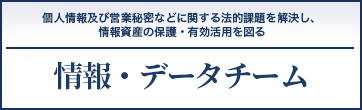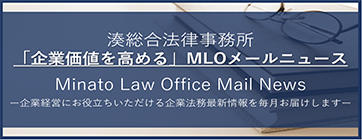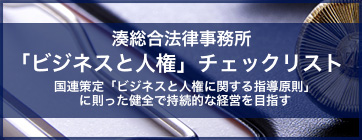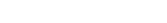▷法的手続きの進め方
タイトル..
1:民事調停
・話し合いは続けてきたけど、病院と患者の間でうまく話がつかない。
・最終的には合意に至りそうだが、どう話したらいいのかわからない。
このような場合は、是非、民事調停の利用をお薦めします。
民事調停とは、簡単に言うと、>話し合いの場が裁判所に移っただけです。裁判官と一般市民から選ばれた調停委員が関与します。病院側と患者側が同席して一度に話をするのではなく、調停委員が双方の話を交互に聞いて、話をまとめてくれます。
事務の方や看護師の方は、未収診療報酬の交渉に辟易とされていることと思いますが、この制度を利用すると非常に楽になります。訴訟に比べて手続も簡単ですし、費用も非常に低額ですみます。(当事務所でも申立書のフォームを提供しています。)
2:支払督促
・病院の近くに住んでいる患者
・未収金が5万円ほどあるので誠実に交渉を続けてきたが、埒が明かない。
・財産はあるようなので、強制的に取り立てたい。
このような場合は、支払督促です。これは書類審査だけの簡便な手続です。裁判所に行く必要もありません。(こちらも、当事務所でフォームを提供しています。)
但し、遠方の患者、または引っ越された場合は、この方法は使わないで下さい。
払ってもらえずに、異議を申し立てられてしまうと、通常の民事訴訟手続に移行してしまい、管轄は債務者の住居地になってしまうからです。これでは往復の交通費の方が診療報酬の未回収額より多額になってしまうなど、泣くに泣けない状況に陥ってしまいます。
3:少額訴訟
・入院費が50万円ほど未払いになっているが、病院と患者の話し合いがつきそうになく、判決をもらいたい。患者の住所地が遠隔地で、支払督促はやりたくない。
60万円までの場合、少額訴訟という非常に便利な制度があります。
少額訴訟を弁護士に依頼される場合もありますが、少額訴訟はそもそも本人でできるよう裁判所も比較的手厚い対応をしていますし、弁護士費用がもったいないと思います。
これは、病院近くの簡易裁判所で申立ができ、遠隔地の患者さんでも、病院のそばの裁判所を管轄とできますので、こちらに来てもらうことができます。少額訴訟手続は、原則としてその日のうちで審議を終了して、判決が出ます。
訴訟ですから、本来的には病院の理事長が行かねばなりませんが、実際には代理人許可申立によって、事務長が代理人として訴訟対応することができます。
4:簡易裁判所における訴訟
・入院関連費未収額が130万円。到底協議できないので、判決により強制執行して回収したい。院長は多忙なので、事務長が代理人となって解決したい。
140万円までは、簡易裁判所における訴訟となります。
簡易裁判所も代理権許可申立をすると、事務長があるいは訴訟担当者が代理人として訴訟対応を行うことができます。
簡易裁判所は代理人を付けずに本人申立てで訴訟が行われることの多い裁判所ですから、比較的当事者に手厚い対応をしており、司法委員が和解交渉について仲介の労をとってくれたり、各種申立て手続等についても、事件相談室に行けば、全部やり方を教えてもらえたりします。
5:地方裁判所における訴訟
・入院関連費未収300万円。到底協議できないので、判決により強制執行して回収したい。院長は多忙なので、事務長が代理人となって解決したい。
140万円を超える場合、地方裁判所における訴訟となります。地方裁判所では弁護士しか代理人になれず、また事件相談室もありませんので、この場合は>弁護士に依頼するのが妥当だと思います。
<医療現場における債権回収の関連記事はこちら>
お困りの方は湊総合法律事務所までご相談ください。
|
<顧問弁護士について> 当事務所では、医療機関と顧問契約を締結させて頂き、様々なリーガールサービスをご提供しております。 顧問弁護士が継続的に医療機関に関する法的なサポートをさせていただくことで、より効果的に法的トラブルを防止し、迅速かつ的確な問題解決を図ることが可能となります。 そのために私達の事務所では法律顧問契約を締結して対応させていただくことをお薦めしております。 担当弁護士が医療機関の状況を把握して、直接お会いして、あるいは電話、メール、Zoomなどの手段を適切に利用して、相談に臨機応変に対応させていただいております。 |
医療機関の関連ページ
- 医療機関
- 医師から当直業務(宿直業務・日直業務)について残業代請求を受けた。 当直手当を支払っているが、別途残業代を支払う必要があるのか?
- 医師から残業代請求を受けた場合、 医療機関(病院、クリニック)としてどのように対応すべきか?
- 医療過誤の責任
- 医療紛争の流れ
- 医療事故の際の患者対応
- 医療事故の際の証拠保全
- 患者に対する説明義務
- 刑事手続きにおける取調べ
- 医療現場における法律知識
- 第1 医療事故に関する法律知識の基礎
- 第2 医療従事者・スタッフのための法律知識
- 医療現場における債権回収
- ▷診療報酬債権の回収
- ▷医療報酬の回収方法を確立しよう
- ▷未収金対策で上手な弁護士の利用方法
- ▷法的手続きの進め方
- ▷未回収のパターンと予防的対策
- コロナ禍の医療機関・病院における労務問題
取扱分野
ご相談のご予約はこちらから



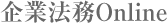
-300x72.png)
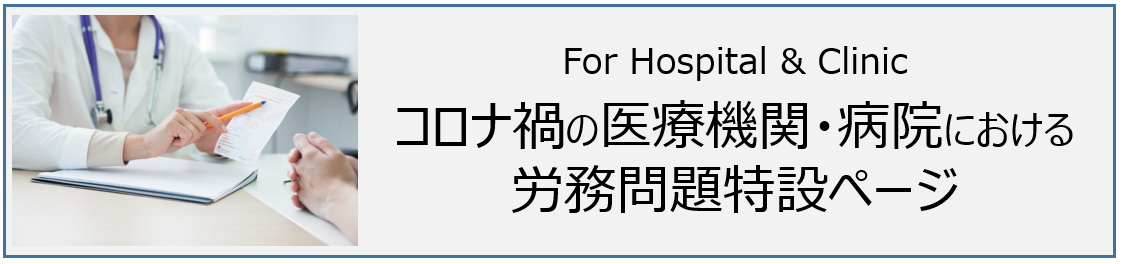
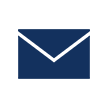 でのお問い合わせは
でのお問い合わせは