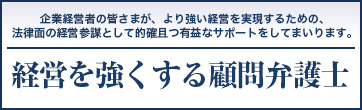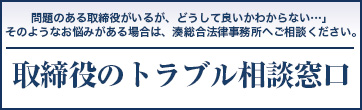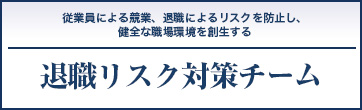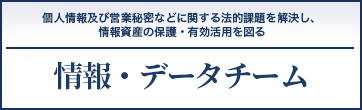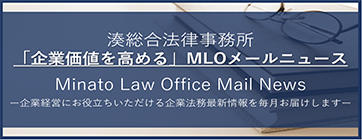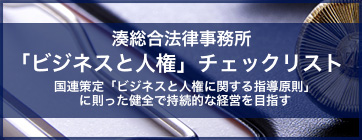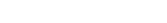検査・手術における説明と同意の取得
タイトル..
検査・手術における説明と同意の取得
Q 医師の判断で、検査や手術の同意書を取得せず、また説明が不十分なまま検査・手術が行われることがあります。医師は自分で責任を取ると行っていますが、検査や手術に関与した看護師や検査技師として責任を問われる可能性はないでしょうか。
A 看護師の責任が問われる可能性も否定できません。したがって、同意書を取得する運用を行うべきです。
1 看護師や検査技師等の責任について
従来は、看護師や検査技師等の医療従事者は、医師の手足であると捉えられていましたが、近時ではそうではなく、医師と協働して医療に従事する専門家と捉えられることが多くなってきました。
近時の裁判例においても、「看護師は、保助看法37条のもとで医師の指示により相対的医療行為を行うことができるが、自らの知識・経験に照らし合わせて医師の指示内容に疑問を有する場合には、再度医師に指示内容を確認すべき義務がある」と判示し(京都地裁平成17年7月12日判決参照)、医師とは別個に看護師の過失が認定される可能性が示唆されております。
そうだとすると、例えば説明が不十分なまま検査等が行われて、その後、当該患者に医療事故が生じた場合、説明が不十分であることを知りながら漫然と検査等を実施した看護師や検査技師等にも説明義務違反が認められるとして、責任を問われる可能性は否定できないと考えられます。
2 患者に対し説明を行う意義について
(1)身体への侵襲に対する患者の同意
手術や検査等の医療行為は、患者の身体への侵襲を伴うものであるところ、患者の同意がなければ、原則として、身体への侵襲を正当化することはできません。
それゆえ、患者の同意なく、手術や検査等の医療行為が行われて医療事故が発生した場合、たとえ当該行為が医学的に正当なものであったとしても、医師等に、当該医療行為について、民事上または刑事上の責任が発生する可能性があります。このように、医療機関が患者に対し、身体への侵襲を伴う医療行為を行う際には、患者の同意を得ることが欠かすことはできないといえます。
(2)患者に対する必要な情報の提供
もっとも、患者からの同意をただ取得すればいいのではなく、手術や検査等の医療行為を受けるかどうか、または、どのような医療行為を受けるかについては,患者自らが決定すべき事項である以上、医療行為の実施及び選択に関する決定は、実施される医療行為の目的や内容を患者が理解した上で行わなければ、患者自身による意思決定がなされたとはいえません。
そこで、医師は、手術や検査等の医療行為を行うに先立って、患者がその目的や内容を理解し、当該医療行為を受けるかどうかを判断するために必要な情報を提供する義務を負っているといえます。
3 患者から書面で同意を得る意義等について
(1)同意の存在を示す証拠となること
まず、患者からの同意は、口頭であろうと書面であろうとどちらでも構わないものです。なぜなら、重要なのは、患者が医師から必要な説明を受けた上で医療行為の実施に納得し同意したかどうかであるからです。
このように、患者から書面で同意を得ることは不可欠ではないのですが、患者からの同意書があれば、患者や家族との間で紛争になった場合に、口頭での同意のみしかない場合と比べて、患者による同意の存在を立証することが容易になります。
なお、説明の結果を証拠として残すためにも、同意書の中には、説明の中身の記載をしておくことにします。そして、患者に対する説明の際に、説明書等の書面を交付した場合には、渡した説明書を必ずコピーして、そのコピーを診療記録に綴り、別紙説明書を渡して口頭で説明とカルテに記載して、説明した事実を日時・場所とともに明記しておくようにしてください。
(2)医療従事者間において同意の有無を確認することができる
どのような内容の医療行為につき、患者から同意が得られているかを書面で明確にしておくことは、医療従事者間の認識を共通化する上でも役立ちます。
すなわち、説明の中身が記載された同意書を得ることにより、検査技師も、患者が医師からどのような説明を受けた上で同意を得ているのかが明らかになるという点で、安心して検査を実施することができます。
(3)同意書の存在を検査等の実施条件とすること
患者に対する説明が不十分なまま検査等が実施された後に生じた医療事故について、看護師や検査技師等が責任を問われないようにするためには、同意書がない場合には、検査等を実施することができない体制を構築することが必要といえます。
お困りの方は湊総合法律事務所までご相談ください。
| <顧問弁護士について> 当事務所では、医療機関と顧問契約を締結させて頂き、様々なリーガールサービスをご提供しております。 顧問弁護士が継続的に医療機関に関する法的なサポートをさせていただくことで、より効果的に法的トラブルを防止し、迅速かつ的確な問題解決を図ることが可能となります。 そのために私達の事務所では法律顧問契約を締結して対応させていただくことをお薦めしております。 担当弁護士が医療機関の状況を把握して、直接お会いして、あるいは電話、メール、Zoomなどの手段を適切に利用して、相談に臨機応変に対応させていただいております。 こうすることにより問題発生前に法的トラブルを防止し、 医療機関の価値を高めることを可能としています。 法律顧問料はかかりますが、結果としてコストの削減にも繋がっていきます。 ▷顧問契約についての詳細はこちらに掲載しております。是非ご参照ください。 |
医療機関の関連ページ
取扱分野
ご相談のご予約はこちらから



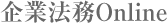
-300x72.png)
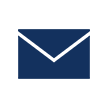 でのお問い合わせは
でのお問い合わせは