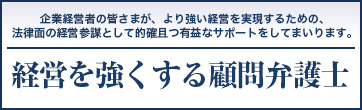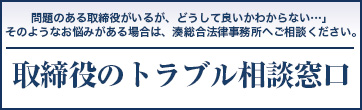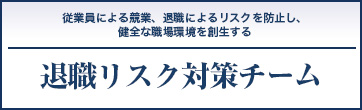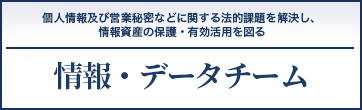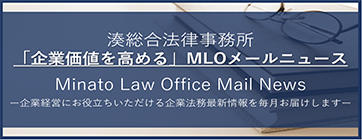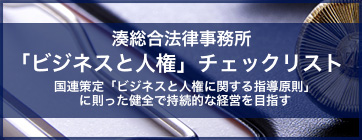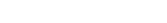企業におけるESG対応
タイトル..
▷湊総合法律事務所のビジネスと人権法務コンサルティングのご案内
企業におけるESG対応
1 ESGが提唱されるまで
(1)国連グローバルコンパクト
20世紀後半にかけてグローバル化が急速に進む中、グローバル化の負の側面が顕著になってきました。それまではグローバル課題は、国家や国際機関が解決を図ろうとしてきましたが、それだけでは解決ができない状況になってきたのです。そこで、コフィー・アナン国連事務総長(当時)は、1999年1月の世界経済フォーラムにおいて、企業にグローバルな課題解決への参画を求め、世界の経営トップに対し、「人間の顔をしたグローバリゼーション」への取組を促しました。そして、「世界共通の理念と市場の力を結びつける力を探りましょう。民間企業の持つ創造力を結集し、弱い立場にある人々の願いや未来世代の必要に応えていこうではありませんか。」と訴えたのです。
こうした努力により、「国連グローバルコンパクト」が誕生し、企業が人権や労働、環境、腐敗防止などの原則を経営方針や戦略に取り組むことが求められるようになりました。
国連グローバルコンパクトは、2015年7月時点において、160か国の8300企業により署名されるまでになり、企業による持続可能性のための正解で最大の自発的なイニシアティブになっています。
国連グローバルコンパクトが、経営に持ち込むことを要求される事項は「国連グローバルコンパクトの10原則」として、以下の表に記載されている10の原則が示されています。
| 人権 | 原則1:人権擁護の支持と尊重
原則2:人権侵害への非加担
|
| 労働 | 原則3:結社の自由と団体交渉権の承認
原則4:強制労働の排除 原則5:児童労働の実効的な廃止 原則6:雇用と職業の差別の撤廃 |
| 環境 | 原則7:環境問題の予防的アプローチ
原則8:環境に対する責任のイニシアティブ 原則9:環境にやさしい技術の開発と普及 |
| 腐敗防止 |
原則10:教養や贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗防止の取組
|
(2)国連環境計画・金融イニシアティブ
金融は、企業や事業に必要とされる資金を効果的に配分する役割を担っています。その責任を果たすためには、近視眼的にならずに、長期的な展望に立って、投資先企業の財務に関する分析に加え、従業員や取引先、顧客、地域コミュニティなど、企業が社会に与える影響や環境に及ぼす影響などをさまざまな角度から把握し、さらに、企業の持続可能性についても十分に考慮して投資の意思決定を行うことが、持続的な運用において重要となります。
こうした観点から国連環境計画と金融業界とのパートナーシップとして国連環境計画・金融イニシアティブが策定されました。
2 ESGが投資のメインストリームに
(1)国連責任投資原則(PRI)
国連グローバルコンパクトと国連環境計画・金融イニシアティブの二つのイニシアティブの流れを受け、経済効率性が高く、持続可能なグローバル金融システムこそが長期的な価値を創出するとの考え方のもとに、2006年にコフィー・アナン国連事務総長が、「ESG」を投資判断の要素に入れて、リスクを管理するとともに長期の持続的な運用を目指す、責任投資原則(PRI)を提唱しました。
このESGこそがEnvironment(環境)、Social(社会)、Governance(企業統治)の三つの言葉の頭文字であり、投資判断においてこれらの非財務的な要素を重視すべきことが提唱されることになったのです。
(2)PRIの目的
PRIは、署名機関により構成される国際的ネットワークと協力し、責任投資原則の6つの原則を実践することを目的としています。
この6つの原則とは以下のとおりです。
【PRIの6つの原則】
- 私たちは投資分析と意思決定のプロセスにESG課題を組み込みます。
- 私たちは活動的な所有者となり、所有方針と所有習慣に ESG問題を組入れます。
- 私たちは、投資対象の企業に対してESG課題についての適切な開示を求めます。
- 私たちは、資産運用業界において本原則が受け入れられ、実行に移されるよう働きかけを行います。
- 私たちは、本原則を実行する際の効果を高めるために、 協働します。
- 私たちは、本原則の実行に関する活動状況や進捗状況に関して報告します。
(3)PRIの6つの原則の意義
このPRIの6原則はESGを理解する上で最も重要であり、企業経営においても無視することはできません。
すなわち、第1原則は、機関投資家が投資対象を分析し、投資するか否かの意思決定する際に、対象企業が環境・社会・ガバナンスという非財務状況を充足しているかを判断して、それが不合格なら投資されないことを意味します。温暖化ガス排出に加担しているとか、サプライヤーに強制労働が認められるなどが発覚した場合には、投資家からの投資が得られないことになりかねないのです。
同様に第2原則は、たとえば投資している企業の議決権の行使の態様についてもESGの観点から判断して、問題があるときは議案について賛成が得られないことになりますし、第3原則により、機関投資家から企業経営上、ESG課題についてどのような取組をしているのかを開示を求められることになり、これに対して適切な説明ができないときは、投資対象から外されることもあり得るわけです。
更には、第4原則により、こうした動きを資産運用業界全体に浸透させて実行に移されるよう働きかけていくというのですから、今後はますます投資の世界はESG重視の方向に進んでいくことになるわけで、いよいよ企業はこの流れを無視することはできなくなってきています。
(4)PRIを加速させる大事件の発生
こうした流れを大きく加速させる大事件が発生しました。
アメリカ合衆国の投資銀行であるリーマン・ブラザーズ・ホールディングスが2008年9月15日に経営破綻したことに端を発して、連鎖的に世界規模の金融危機が発生したいわゆるリーマンショックです。
リーマン・ブラザーズは、負債総額約6000億ドル(約64兆円)というアメリカ合衆国の歴史上、最大の企業倒産により、世界連鎖的な信用収縮による金融危機を招きました。
この事件では、それまでの短期的利益を追求する姿勢を反省し、中長期的なサスティナブルな視点が重要であることが認識されました。
この事件を契機としてESG投資の流れが確かなものとされるようになっていきました。
(5)PRIの現状
このような流れを経てPRI原則署名機関は、2019年3月時点で2,300機関、運用規模は85兆ドルを超える規模となっています。
PRIには年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が2015 年9月に署名しており、2019年5月時点で日本の署名機関数は75社、第10 位となっています。
今や、ESG投資は、投資のメインストリームとなったといっても過言ではない状況にいたっています。
3 ESGの具体的内容とは
ESG投資において重視される要因は、何が、企業の中長期的な成長を基礎づけるのか、逆に言えば、企業の中長期的成長を阻むものは何かということです。
ESGのそれぞれについてみていきましょう。
(1)Environment(環境)
- 温室効果ガス・気候変動・異常気象・自然災害問題
- 大気・水の汚染問題
- 環境保全問題
- 森林破壊問題
- 生態系保全・生物多様性の逸失問題
- 座礁資産問題(温室効果ガス排出抑制政策導入による化石燃料資産価値の目減り)
- 廃棄物管理問題
- 環境負荷低減問題
など
(2)Social(社会)
- 児童労働・強制労働その他労働基準・慣行問題
- サプライヤー管理
- 地域紛争問題
- ダイバーシティ問題
- ジェンダー問題
- 製品・サービスの安全・責任に関する問題
- 医療アクセス・医薬品の倫理的開発問題
- 安全衛生問題
- データセキュリテイ・サイバーセキュリティ・プライバシー保護
など
(3)Governance(企業統治)
- 取締役会・社外役員・監査役会・独立性・多様性問題
- 監査・内部統制問題
- 内部通報制度
- 経営陣の報酬問題
- 株主の権利
- 利益相反管理
- 贈収賄・汚職問題
- 会計リスク問題
- 租税回避・税金の透明性問題
など
4 ESG経営において重要なこと
以上に掲げた各事項は、これまでは企業における環境・社会・ガバナンス上の各課題として個別的に捉えられてきたことが多いと思います。
しかし、責任投資原則(PRI)の署名機関からは、これらの事項は、投資判断の重要事項とされますから、企業としては個別的問題としてではなく、総合的に考えて、自社のリスクはどこにあるのかということを十分に検討して、優先順位をつけて克服していく必要があります。
そして、これらは、機関投資家だけでなく、NGOや市民団体も注目しているところであり、企業における取組を適切に開示して、対話をしていくことが求められることになります。
今後の企業経営ではますますこうした対応を専門的に行っていく必要がでてくるということを肝に銘ずる必要があります。
書籍のご案内

弁護士 湊信明(共著)
日本経済新聞出版
「成功へと導く ヒューマンライツ経営~人権リスク・マネジメントで勝ち抜く~」
(ビジネスと人権に関する行動計画 2020年10月政府策定に対応)
第1章:第5次産業革命の生存戦略
第2章:「ビジネスと人権に関する指導原則」が企業の成長を加速する
第3章:人権問題・社会課題を解決する企業が飛躍的に成長する
第4章:「ビジネスと人権」に関する行動計画のココを経営に取り込む
第5章:企業行動は国別行動計画からのステップアップが必要 他
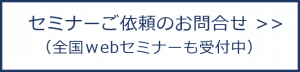 当事務所では、SDGs、ビジネスと人権に関する指導原則、ESGに関するセミナーを受け付けておりますので、ご希望の皆さまは、是非ご連絡ください。 当事務所では、SDGs、ビジネスと人権に関する指導原則、ESGに関するセミナーを受け付けておりますので、ご希望の皆さまは、是非ご連絡ください。 |
| トムソンロイター社 ASIAN LEGAL BUSINESS(2021年12月号)に 「ESGと企業経営」についての記事(弁護士 湊信明)が掲載されました。 ▷詳しくはこちらをご覧ください。 |
| 【動画配信のご案内】 弁護士 湊信明が、分かりやすく解説しております。是非ご覧ください ※「中小企業法務チャンネル(株式会社プロローグ)」にてネット配信中◆ESG経営とビジネスと人権に関する指導原則 ①GPIFの責任投資原則に則ったESG投資とは?>>>②セールスフォース社の事例など取引先の強制労働・人権侵害と人権デューデリジェンス>>>③イギリス現代奴隷法と介護等の技能実習生問題、中国ウイグル自治区人権問題>>>④東京オリンピック・パラリンピックと調達コードの策定>>>◆SDGsとは? ①ラナプラザ崩壊事故の悲劇と世界のカカオ豆児童労働・強制労働の実態。 ダボス会議のグレートリセット>>> |
②国連の2030アジェンダから見る中小企業・経営者としてできること・取り組み事例>>>
③ゴミ・環境問題と対策。食品のトレーサビリティとAI・ブロックチェーン技術の融合>>>
◆ESG投資とサスティナブル経営。
中小企業の経営者として環境問題・人権問題・企業統治に向き合う >>>
SDGs ビジネスと人権 ESG関連 講演資料ダウンロード
ビジネスと人権・SDGs・ESGの関連ページ
- ビジネスと人権
- 日本企業がビジネスと人権に取り組むべき理由
- 日本企業が人権方針を策定する意義と具体的な方策
- 人権デュー・ディリジェンスの意義と具体的な方策
- ビジネスと人権における「救済」の意義と企業への適用
- 企業が取るべきアクション:ビジネスと人権に関する国内行動計画
- 「ビジネスと人権」各社の取組事例
- トヨタ自動車株式会社における「ビジネスと人権」に関する取組み事例(2024年2月現在)
- 花王における「ビジネスと人権」に関する取組み事例(2024年6月現在)
- ANAグループにおける「ビジネスと人権」に関する取組み事例(2024年6月現在)
- 味の素グループにおける「ビジネスと人権」に関する取組み事例(2024年4月現在)
- 企業経営におけるSDGsへの取り組みとその重要性
- 企業におけるESG対応
- 「ビジネスと人権」達成度診断
- CSR・ESG法務チェックリスト
- 実践企業法務チャンネル
- ESG・SDGs・ビジネスと人権に関する指導原則 講演資料ダウンロードお申し込み
- SDGsで企業利益と社会貢献を同時に実現する 講演資料ダウンロードお申し込み
取扱分野
ご相談のご予約はこちらから



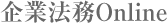
-300x72.png)


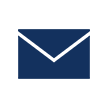 でのお問い合わせは
でのお問い合わせは