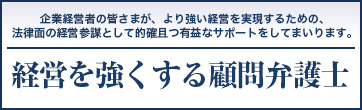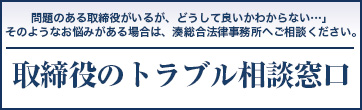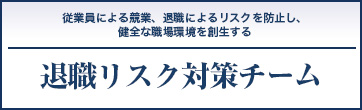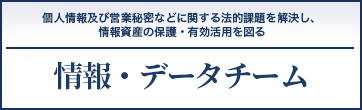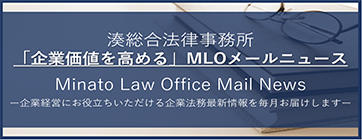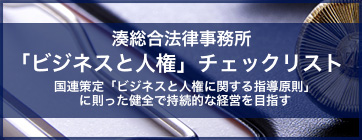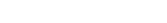ビジネスと人権に関する指導原則
タイトル..
▷湊総合法律事務所のビジネスと人権法務コンサルティングのご案内
ビジネスと人権に関する指導原則
1 「ビジネスと人権に関する指導原則」とは
これまでに、企業が事業活動やサプライチェーンを通じて児童労働・強制労働等の労働問題、消費者被害、地域住民に対する被害など、ステークホルダーに負の影響を与えている数々の事件において問題化されてきました。
冒頭で述べたバングラデシュのラナ・プラザ事件がその一例です。
また、1990年代後半には、米国大手スポーツ用品メーカーであるナイキ社が、その製造委託先において、サッカーボールの生産で児童労働をさせていたことや、アパレル商品の生産で劣悪な労働環境下で働かされていた事実が発覚し、全米の大学をはじめとした不買運動に発展した事件がありました。
米国アップル社がiPhoneなどの製造を委託している大手EMSフォックスコンの中国工場において、NGOから労働環境や安全衛生上の問題があると指摘されていたところ、短期間に10人以上の労働者が自殺するという事件が発生し、世界中に報道され著しいイメージ低下を招いたという事件がありました。
そこで、国連は、こうした問題に対処すべく、2011年に国連人権理事会において、「ビジネスと人権の指導原則」(以下、単に「指導原則」ともいいます。)が採択するに至りました。
この原則は、ESGとSDGsの大前提であり、その理解なくしてESG・SDGsの実現はあり得ません。
企業経営においても必ず理解し対応すべき原則であり、これを軽視していると大きなダメージを被ることになりますから特に要注意です。
【ビジネスと人権に関する指導原則(解説付き)】
https://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/resolutions_reports/hr_council/ga_regular_session/3404/
2 「ビジネスと人権に関する指導原則」の3つの柱
指導原則は、3つの柱によって構成されています。
第1の柱は人権を保護する国家の義務、第2の柱は人権を尊重する企業の責任、第3の柱は救済へのアクセスとなっています。
このHPでは、企業経営に関するものですので、第2の柱と第3の柱のうち企業経営に関するものについて説明していきます。
3 人権を尊重する企業の責任「A 基本原則」
(1) 指導原則11(国際人権尊重責任)
ア 内容
「企業は人権を尊重すべきである。それは,企業が他者への人権侵害を回避し,企業が関与した人権への悪影響に対処すべきことを意味する。」
イ 解説
指導原則11の解説には、「人権を尊重する責任は、事業を行う地域にかかわらず、すべての企業に期待されるグローバル行動基準である。・・・その責任は、人権を保護する国内法及び規則の遵守を越えるもので、それらの上位にある。」と記載されています。
この企業の人権尊重責任は、関係法令の遵守義務の上位に位置するとしたことに極めて重要な意義を有しています。
指導原則は企業に対して強制力を有するものではありませんが、仮に、企業側が所在する国の法律や進出している先の法律は遵守していると主張しても、当該企業が国際的な人権尊重義務に反しているならば、市民団体・NGOからは、指導原則11を根拠として問題が指摘されることになり、企業側は大きなレピュテーションリスクを負いかねなくなるわけです。
(2) 指導原則12(遵守すべき国際人権)
ア 内容
「人権を尊重する企業の責任は国際的に承認された人権に拠っているが, それは少なくとも,国際人権章典や労働における基本的原則及び権利に 関する国際労働機関(ILO)宣言に規定されている基本的権利に関する 原則等に表明されている人権と理解される。」
イ 解説
ここでは遵守すべき人権の範囲について規定しています。ここで注意すべきことは、日本は、すべての国際人権条約を批准していないということです。日本のみを基準にしていると判断を誤る危険があるので注意が必要です。
国際的に認められた主要な人権の権威あるリストは、国際人権章典(世界人権宣言、及びこれを条約化した主要文書である市民的及び政治的権利に関する国際規約ならびに経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約)とともに、労働における基本的原則及び権利に関する宣言に挙げられたILO中核8条約上の基本権に関する原則となります。
(3) 指導原則13(企業が求められる行動)
ア 内容
「人権を尊重する責任は企業に以下の事項を要求する。
(a) 企業活動による人権への悪影響の惹起またはその助長を回避し,惹起した際には対処すること。
(b) 企業活動と直接関連する,または取引関係による製品もしくはサービス に直接関連する人権への悪影響については,企業がその惹起に寄与していなくても,回避又は軽減に努めること。」
イ 解説
この規定により、企業は、自らの活動により人権に対して負の影響を引き起こしている場合に、その状況に対処しなければならないとされるだけでなく、当該企業がその製造委託先等に対して資本関係等がなくても、製造委託先会社内において人権侵害行為に影響を与えている等の場合には、これに対して対処等しなければならないことになります。
▷湊総合法律事務所のビジネスと人権法務コンサルティングのご案内
4 人権を尊重する企業の責任「B 運用上の責任(企業方針によるコミットメント)」
(1) 指導原則16(企業方針によるコミットメント)
ア 内容
「人権を尊重する責任を定着させるための基盤として,企業は,この責任を果たすためのコミットメントを,以下の要件を満たす企業方針のステートメントを通して表明するべきである。
(a) 企業の最上層レベルによる承認があること。
(b) 内部及び/または外部の適切な専門家により情報提供を受けたこと。
(c) 企業の従業員,取引関係者及びその他企業活動・製品もしくはサービス に直接関係している者に対する人権配慮への期待が明記されていること。
(d) 一般に入手可能で,かつ内外問わず全従業員,共同経営/共同出資者及び その他関係者に周知されていること。
(e) 企業全体に定着させるために企業活動方針や手続に反映されていること。」
イ 解説
この規定も大変大きな影響があります。すなわち、企業のトップを含めた経営層が、人権尊重責任についてどのような姿勢をとるのかを明確に打ち出させ、約束させることにより、NGOや市民団体は、当該企業が人権に対して、コミットメントに反する対応をしていた場合には、容易に責任追及、ないしは是正の要求を行い得ることになります。
5 人権を尊重する企業の責任「B 運用上の責任(人権デュー・ディリジェンス)」
(1) 指導原則17
ア 内容
「企業は、人権への悪影響を特定し、予防し、軽減し、対処方法を説明するために、人権デュー・ディリジェンスを実施するべきである。この手続は、現実の及び潜在的な人権への影響の評価、調査結果の統合と対処、対応の追跡調査、対処方法の周知を含むべきである。企業による人権デュー・ディリジェンスは以下の要件を満たすべきである。
(a) 企業がその活動を通じ惹起または助長するおそれのある人権への悪影響, または取引関係による、企業活動、製品もしくはサービスに直接関連し得る人権への悪影響を含むこと。
(b) その複雑さは企業の規模、人権に対する重大な影響へのリスク、企業活動の性質や状態に応じて異なること。
(c) 人権に関するリスクは企業活動の状態やその変遷により時間とともに変化する可能性があることを踏まえ、継続的に行うこと。」
イ 解説
上述したラナ・プラザ事件、ナイキ事件、アップル事件は、いずれも製造委託先において発生した人権侵害行為の調査、追跡、是正を怠ったことから発生した事件であり、そのことから責任追及を受けることになり、甚大な損害を被ることになりました。
自社が積極的に人権侵害行為を行っている場合は別として、まったく別会社である製造委託先等の場合には、当該会社の中で行われている人権侵害行為に気が付くことは通常困難でしょう。
しかし、製造委託先会社は、コストを安く抑えるために児童労働や長時間労働をさせていることがあり、発注会社の方は、こうした安い労働力を利用して安価に製品を仕入れることを可能にしていることがあります。このような場合などには、発注者の側で人権侵害の事実がないか、それに加担しているようなことがないかについて、積極的にしっかりと調査をさせ、追跡し、是正させることにより、人権侵害を防止させる必要があります。
この指導原則はそのための要件等について規定するものです。
人権デュー・ディリジェンスの具体的方法については、日本弁護士連合会が2015年に発行した「人権デュー・ディリジェンスのためのガイダンス(手引)」に詳しく説明されているので、是非ご参照ください。
【人権デュー・ディリジェンスのためのガイダンス(手引)(日本弁護士連合会)】
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2015/opinion_150107_2.pdf
(2) 指導原則19(影響評価・プロセス組入・適切な措置)
ア 内容
「企業は、人権への悪影響を予防、軽減するため、人権への影響評価で得た調査結果を全社的に関連する職務部門及び手続に組み込み、適切な措置をとるべきである。
(a) 実効的に調査結果を組み込むには以下が必要である。
(i) そのような影響に対処する責任が、企業内の適切な階層の適切な職務部門に割り振られていること。
(ii) 企業内の意思決定、予算配分、監督手続が、そのような影響への実効的な対応を可能にしていること。
(b) 適切な措置は以下に応じて異なる。
(i) 企業が悪影響を惹起または助長しているか、それとも商取引関係 先による企業活動、製品またはサービスが悪影響に直接関連していることにより関与しているに過ぎないのか。
(ii) 人権への悪影響に対処する場合の企業の影響力の範囲。」
イ 解説
企業がサプライチェーン等を通じて人権侵害を助長し、または助長している場合、その助長を止め、または防止するために、その企業は、必要な手段をとるべきであり、残存するどんな影響をも軽減するため、可能な限りその影響力を活用していかなければなりません。
企業がサプライチェーン等に対してこうした影響力を行使していく上で有効な手段がいわゆるCSR条項です。
CSR条項とは、サプライヤーなどとの契約において、サプライヤーなどの取引先に対し、CSR行動規範の遵守や人権DDの実施などを義務づける条項のことを意味します。
すでに述べたように、経団連の企業行動憲章は、サプライヤーにも人権保障責任を負わせるとしていいます。日本には、技能実習生・外国人労働者問題などの人権問題を抱えていますから、CSR条項をどう規定するかがこれからの企業法務のなかでより重要性を帯びてくるでしょう。
一方、CSR条項は、人権侵害を起こしたサプライヤーとの取引解消のための手段としてのみ利用されたり、サプライヤーに責任転嫁する、あるいは2次以下のサプライヤーにCSRの過度な遵守を求めるなど過大負担が生ずる危険性もあります。今後は、中小サプライヤーの保護をいかに図るべきかも十分に検討する必要が出てくるものと考えられます。
このCSR条項についても、「人権デュー・ディリジェンスのためのガイダンス(手引)」に詳しく説明されているので、是非ご参照ください。
【人権デュー・ディリジェンスのためのガイダンス(手引)(日本弁護士連合会)】
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2015/opinion_150107_2.pdf
(3) 指導原則23(あらゆる状況で企業がすべきこと)
ア 内容
「いかなる状況においても、企業は以下のようにすべきである。
(a) どこで活動を行う場合も、適用可能な全ての法令を遵守し、国際的に承認された人権を尊重する。
(b) 相反する要請に直面した場合は、国際的に承認された人権の原則を尊重する方法を追求する。
(c) いかなる場所で活動を行う場合も,著しい人権侵害を引き起こす,または助長するリスクを,法令遵守の問題として扱う。」
イ 解説
ここで重要なことは、企業は国際的に承認された人権の原則を尊重すべきであり、仮に当該原則を当該企業が属する国では人権として認められていなかったとしても、法令遵守の問題として扱わねばならないとされたことです。
したがって、企業としては、常に国際的に承認された人権が何か、それに違反する活動はしていないかに注視しつつ経営をする必要があり、それを怠ると責任追及がなされることになりますから注意が必要です。
▷湊総合法律事務所のビジネスと人権法務コンサルティングのご案内
6 人権を尊重する企業の責任「B 運用上の責任(非国家主体による苦情処理の仕組み)」
(1) 指導原則29(企業による苦情処理メカニズムの確立)
ア 内容
「苦情への対処が早期になされ、直接救済を可能とするように、企業は、負の影響を受けた個人及び地域社会のために、実効的な事業レベルの苦情処理メカニズムを確立し、またはこれに参加すべきである。」
イ 解説
人権侵害等の負の影響を受けた個人あるいは地域社会を救済するため、企業に対して苦情がなされた場合には、苦情処理メカニズムを確立するか、自社外に苦情処理メカニズムがあればそれに参加することにより、早期に直接的に救済を可能とすべきことを要請するものです。
指導原則がこのような要請をしているにも関わらず、自社内あるいは社外において直接的な実効的な救済が得られない場合には、本原則違反として追及されることになりますから注意を要します。
7 「ビジネスと人権に関する指導原則」の企業経営への影響
上述した2013年にバングラデシュで発生したラナ・プラザ事件を例にしていえば、発注先企業としては、従来であれば、「製造委託先の現地企業は、当社とは資本関係もない別法人であり、当該製造委託先企業の問題であって当社には責任がない。」とか、「現地の法律は遵守している。」などと言えたかもしれません。
しかし、「ビジネスと人権に関する指導原則」が採択されたことにより、その指導原則11・12から、そのようなことは言えなくなりました。また、指導原則23から、国際的人権侵害は法令遵守問題となり、法令遵守義務違反を主張できるようになりました。
企業としては、指導原則17・24にあるように、事前に優先事項を定めて人権デュー・ディリジェンスを行ってリスクを解決しておく必要に迫られるようになったといえます。
このように指導原則が採択されたことにより、メディアやNGOは、企業が環境・労働・社会問題に対して間接的に及ぼす悪影響に対し、指導原則を根拠として、「人権侵害への加担」として追及し行動するようになってきたのであり、極めて大きな影響があります。
8 国別行動計画(NAP)
(1) 指導原則は国別行動計画の制定を要請
「ビジネスと人権に関する指導原則」は、法的な強制力はありませんが、各国政府に対し、企業に遵守を促すための計画(「国別行動計画(NAP)」)を策定することを要請しています。
イギリスやオーストラリアでは、現代奴隷法を制定して、一定の規模の企業に対し、指導原則遵守を法的義務化しています。
日本でも今後は、同様の法律ができる可能性があり要注意です。
(2) イギリス現代奴隷法
イギリスは、指導原則の要請にしたがい、2015年3月に現代奴隷法を制定しました。
この法律では、イギリスに現地法人を持つ一定規模(年間売上3,600万ポンド約60億円)以上の企業に適用され、事業の一部でも行っていれば外国企業に対しても適用を受けることとされています。
したがって、日本企業もこうした要件に該当すれば容易に同法の規制を受けることになります。この法律にいう奴隷的拘束には、物理的拘束である必要はありません。多額の借金のために働かざるを得ないなど経済的拘束も含まれます。日本企業が技能実習生を使っていた場合これに該当する可能性がありますから要注意です。
イギリス現代奴隷法は、自社のサプライチェーンにおいて、現代奴隷が存在するための手続に関する声明を毎年度行うことを要求しています。
この声明を行わないと、内務大臣は、高等裁判所を通じて、企業に規制の遵守を要求する執行命令を出すよう要求することが可能となります。そして、執行命令に従わないと、無制限の罰金を課されることとされています。
仮に罰金を課されなくても、同法に違反すれば、消費者・投資家・NGOから批判を受け、大きなレピュテーションリスクが生ずることになり、企業としてはダメージを被ることになります。
日本企業もイギリスに一部でも拠点がある場合、あるいは、そのサプライヤー企業である場合には、現代奴隷法の適用・影響を受ける可能性がありますから、対応上、十分に注意を要します。また今後、同様の現代奴隷法が各国で策定される可能性ありますので要注意です。
(3) 日本における国別行動計画(NAP)の策定
日本政府は、2016年11月、ビジネスと人権国別行動計画を策定する旨を発表し、2020年2月、外務省が「ビジネスと人権」に関する行動計画原(案)(2020-2025)を発表するに至りました。
おそらく遠からずほぼこの内容で確定するものと考えられます。行動計画原案が確定すれば、今後の日本の企業経営において極めて重要な意義を有することになります。また日本においても日本版現代奴隷法が成立する可能性もあるでしょう。
いずれにしても、「ビジネスと人権」に関する行動計画原(案)(2020-2025)の動向については注視し続けていくことが重要です。
【「ビジネスと人権」に関する行動計画原(案)(2020-2025)】
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000198417
▷湊総合法律事務所のビジネスと人権法務コンサルティングのご案内
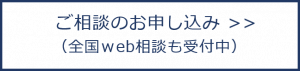 SDGs、ビジネスと人権に関する指導原則、ESGの取り組みをお考えの経営者・CSR 部、法務部、総務部の 皆さまは、湊総合法律事務所にご相談ください。 SDGs、ビジネスと人権に関する指導原則、ESGの取り組みをお考えの経営者・CSR 部、法務部、総務部の 皆さまは、湊総合法律事務所にご相談ください。 |
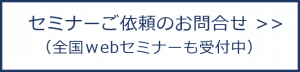 当事務所では、SDGs、ビジネスと人権に関する指導原則、ESGに関するセミナーを受け付けておりますので、ご希望の皆さまは、是非ご連絡ください。 当事務所では、SDGs、ビジネスと人権に関する指導原則、ESGに関するセミナーを受け付けておりますので、ご希望の皆さまは、是非ご連絡ください。 |
湊総合法律事務所HP記事のご案内
書籍のご案内

弁護士 湊信明(共著)
日本経済新聞出版
(ビジネスと人権に関する行動計画 2020年10月政府策定に対応)
第1章:第5次産業革命の生存戦略
第2章:「ビジネスと人権に関する指導原則」が企業の成長を加速する
第3章:人権問題・社会課題を解決する企業が飛躍的に成長する
第4章:「ビジネスと人権」に関する行動計画のココを経営に取り込む
第5章:企業行動は国別行動計画からのステップアップが必要 他
ESG・SDGs・ビジネスと人権に関する指導原則の関連ページ
| トムソンロイター社 ASIAN LEGAL BUSINESS(2021年12月号)に 「ESGと企業経営」についての記事(弁護士 湊信明)が掲載されました。 ▷詳しくはこちらをご覧ください。 |
| 【動画配信のご案内】 弁護士 湊信明が、分かりやすく解説しております。是非ご覧ください ※「中小企業法務チャンネル(株式会社プロローグ)」にてネット配信中◆ESG経営とビジネスと人権に関する指導原則 ①GPIFの責任投資原則に則ったESG投資とは?>>>②セールスフォース社の事例など取引先の強制労働・人権侵害と人権デューデリジェンス>>>③イギリス現代奴隷法と介護等の技能実習生問題、中国ウイグル自治区人権問題>>>④東京オリンピック・パラリンピックと調達コードの策定>>>◆SDGsとは? ①ラナプラザ崩壊事故の悲劇と世界のカカオ豆児童労働・強制労働の実態。 ダボス会議のグレートリセット>>> ②国連の2030アジェンダから見る中小企業・経営者としてできること・取り組み事例>>> ③ゴミ・環境問題と対策。食品のトレーサビリティとAI・ブロックチェーン技術の融合>>> ◆ESG投資とサスティナブル経営。 |
SDGs ビジネスと人権 ESG関連 講演資料ダウンロード
ビジネスと人権・SDGs・ESGの関連ページ
取扱分野
ご相談のご予約はこちらから



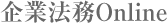


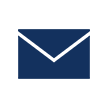 でのお問い合わせは
でのお問い合わせは